 子育て
子育て 🎍年末年始、三世代10人で沖縄へ✈️
年末年始に三世代10人で沖縄旅行へ。LCC利用、国際通り沿いホテル、行程を詰めすぎない工夫など、実際に行ってわかったメリット・注意点を正直にまとめました。家族旅行を検討中の方へ。
 子育て
子育て  不登校
不登校  子育て
子育て  不登校
不登校 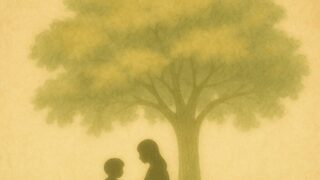 子育て
子育て  不登校
不登校  不登校
不登校  不登校
不登校 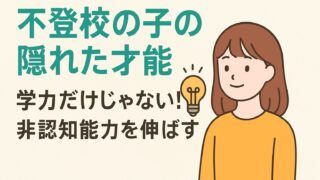 不登校
不登校  不登校
不登校