学校に行かない」と決めた瞬間から、家庭の出費は大きく変わっていきます。
学費が減るどころか、むしろ増えることも多いのが“不登校の現実”。
フリースクールや通信教育、カウンセリング、医療費…一つひとつは少額に見えても積み重なるとかなりの負担に。この記事では、不登校にかかるお金の内訳や具体的な金額例、そして家計と心を守る工夫についてまとめました。
▼不登校は「お金がかかる」のか?
「学校に行かないならお金はかからないのでは?」と思う方もいるかもしれません。
給食費は止められるし、制服や学用品の出費も減るでしょう。
でも実際には、別のところでお金が必要になります。学校という「無料の居場所」がなくなる分、家庭がその役割を補うことになるのです。
▼ 直接的にかかる費用
フリースクール・適応指導教室
フリースクールの費用は、月額3〜10万円ほど。週5で通うと年間100万円を超えるケースも珍しくありません。
公的な「適応指導教室」は無料ですが、利用枠や場所の問題で全員が通えるわけではないのが現状です。
通信教材・オンライン学習
「家で勉強するなら」と、通信教育やオンライン教材を導入する家庭も多いです。
進研ゼミやスマイルゼミは月6,000〜10,000円前後。
オンライン個別指導だと1回5,000円以上かかることも。
塾より安いとはいえ、年間で10万円以上はかかる計算になります。
カウンセリング・医療費
不登校に心の問題が関係する場合、カウンセリングや心療内科の通院も増えます。
1回5,000〜1万円のカウンセリングを月2回受けると、それだけで年間20万円。
医療保険が効く場合もありますが、交通費も合わせると意外に大きな出費です。
▼ 間接的にかかる費用
親の働き方の変化
子どもが家にいる時間が長くなると、親の働き方を変えざるを得ないことも。
パート勤務に切り替えたり、在宅ワークに移行するなどして収入が減るケースも少なくありません。
実はこれが一番大きな「見えない出費」です。
習い事・居場所づくりの追加費用
学校の代わりに居場所を求め、習い事や民間の居場所サービスを利用することも。
プログラミング教室、スポーツクラブ、芸術系の習い事など、1つあたり月5,000〜15,000円。複数かけ持ちすればあっという間に数万円になります。
移動・交通費
スクールや病院が遠ければ交通費もかさみます。片道500円でも月20回通えば2万円。年間にすると24万円近くに。
そんな中、我が家も背に腹は変えられず、いろんなチャレンジをしています。家計管理をはじめから見直し、最終的にはNISAと貯金のダブルで資産管理をしていくことになりました。
【不登校はお金がかかる】少額からの投資デビュー記事はこちら👆
▼公的支援や補助制度はあるの?
現状、日本ではフリースクールに対する公的補助は限定的です。自治体によっては交通費の一部補助や、学習支援員の配置がありますが、家計を大きく助けるほどではありません。
一方、所得に応じて「就学援助制度」で学用品費や給食費が支給されることもあるので、学校や市役所で確認すると良いでしょう。
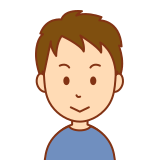
でもさ、“教育無償化”ってニュースで聞くけど、あれって実際どうなってるの?
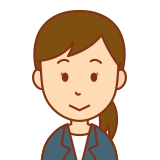
ここからは、“教育無償化”の制度についてわかりやすく解説しますね!
▼教育無償化のしくみを整理してみよう
「教育無償化」といっても、どこまでが対象で、どんな条件があるのか…実際にはちょっと複雑です。ここでは、幼児教育から大学までの流れを表にして整理しました。
教育無償化の対象まとめ(日本)
| 教育段階 | 制度名 | 内容 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 幼児教育・保育 | 幼児教育・保育の無償化 | 3〜5歳は保育所・こども園・幼稚園の利用料が無償。0〜2歳は住民税非課税世帯などが対象。 | 認可施設は全額、認可外は上限あり+「保育の必要性」認定が必要。 |
| 小・中学校(義務教育) | 憲法第26条に基づく無償 | 公立小中は授業料がかからず、教科書も無償。 | ただし給食費・制服・学用品・行事費は自己負担。私立は対象外。 |
| 高校 | 高等学校等就学支援金制度 | 世帯収入に応じて授業料を国が支援。公立は実質無償、私立も多くの家庭で軽減。 | 所得制限あり。支援額は学校によって差あり。 |
| 大学・専門学校など | 高等教育の修学支援新制度 | 授業料・入学金の免除や減額+給付型奨学金。 | 所得制限あり、対象校のみ。2025年度から多子世帯(扶養する子が3人以上)は所得制限なしで対象。 |
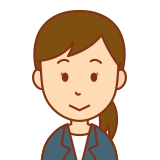
無償って言っても無償化されない部分もあります。
無償化されない部分もある
「無償」といっても、対象は主に授業料。実際に家庭が負担するのは…
- 給食費
- 通学交通費
- 制服や学用品費
- 修学旅行や部活動の費用
などが代表的です。
さらに、不登校でフリースクールを利用する場合は月数万円〜十数万円かかりますが、残念ながら現状は無償化の対象外です(自治体によって独自補助あり)。
多子世帯への拡充
注目したいのは、2025年度から始まった「多子世帯」への拡充です。
子どもを3人以上扶養している世帯なら、所得制限なしで大学や専門学校の授業料・入学金が一定額まで無償になります。
ただしポイントは「扶養している子が3人以上」であること。
上の子が成人して就職し、扶養から外れたら「2人扱い」となり、制度の対象から外れてしまう場合があります。
ここは税情報の反映時期にもよるので、進学時に必ず学校や自治体に確認するのが安心です。
制度を味方にするために
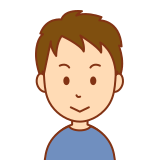
教育費は大きな負担ですが、制度を正しく知っておくと、支出をグッと減らせることがあるんだね。
特に多子家庭や進学を考えているご家庭は、次の点をチェックしましょう。
- 扶養に入っている子どもは何人いるか
- 通う予定の学校が制度対象校かどうか
- 住民税や扶養情報の反映時期
- 所得制限や資産要件があるかどうか
ちょっとした確認で「知らなかった…」と損するのを防げますよ。
▼ 家計を守る工夫と我が家の体験談
我が家も「不登校=家計に直撃」を痛感しました。
最初は焦って色々な教材やサービスに手を出しましたが、長続きしないものも多く、結果的に無駄な出費になったことも。
そこで取り入れた工夫は:
- 無料体験やお試し期間を必ず利用する
- 習い事は「本人が本当にやりたいこと」に絞る
- 在宅ワークで少しでも収入を補う
- 支出は「固定費化」して把握しやすくする
お金を「投資」として考えると、必要な支出と削れる支出の線引きが少しずつ見えてきました。
▼不登校とお金の「見えない負担」
直接的なお金以外にも「機会損失」という形で負担が発生します。
例えば、親が仕事を減らしたことで将来の年金額が下がる、子どもが同世代と違う進路を取ることで進学費用が通常より増える、といった長期的な影響です。
「今だけの問題」と思いがちですが、将来の家計設計にも大きく関わることを忘れてはいけません。
▼まとめ:お金の使い方は「投資」として考える
不登校には確かにお金がかかります。でもそれは「子どもが健やかに成長するための投資」と考えることもできます。
フリースクールや教材が「居場所」や「自信」につながれば、それは何よりの価値です。
家計を守りながら、子どもにとって必要な支出をどう選ぶか。
悩みながらも、親が「味方であること」をお金の使い方から伝えることが、子どもの安心感につながると感じています。
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。
「不登校とお金」「教育無償化」というテーマは、どちらも家庭にとって身近で、でもちょっと重たい話題ですよね。
読んでくださったあなたが、少しでも「そうなんだ」「うちも見直してみようかな」と感じてもらえたら、とても嬉しいです。
教育にかかるお金は大きいけれど、制度を知って味方につければぐっとラクになることもあります。
これからも、一緒に学びながら工夫していきましょう🌸
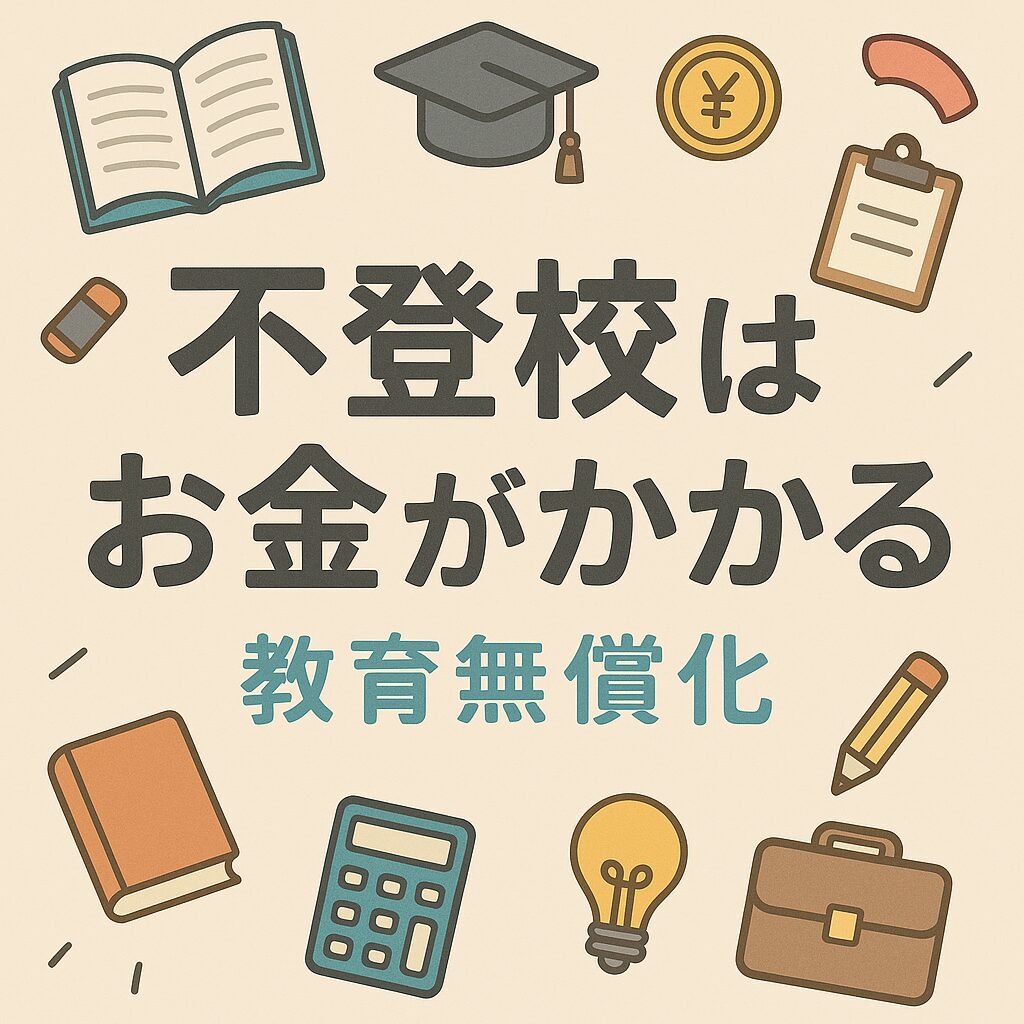
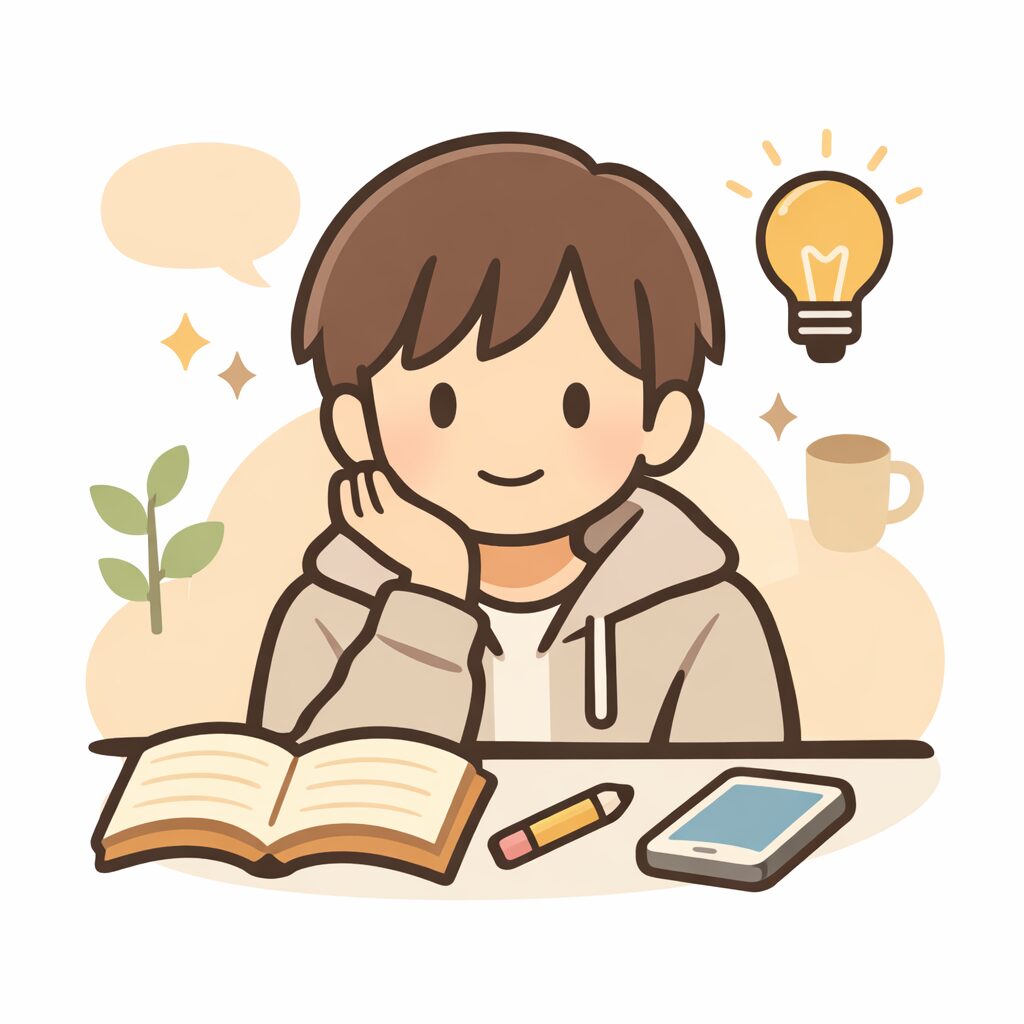


コメント