不登校が長引くと、親が次に心配になるのは「生活リズム」と「勉強の遅れ」。
昼夜逆転で昼間は寝てばかり、夜は元気いっぱい…。
机に向かわない姿を見て「このまま大丈夫なの?」と不安になる方も多いはずです。
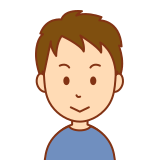
昼夜逆転は、そんなに悪いことではありません!
人間の自然のサイクルであり得ることなんです。
これは不登校の子が通る自然な道。
むしろ焦らずに見守ることが、子どもが再び安心して学びに向かう力につながります。
今回は、昼夜逆転や勉強への不安とどう付き合えばいいのか、3つの工夫を紹介します。
▼昼夜逆転は“通過点”ととらえる

なぜ夜型になりやすいのか
人の体内時計は約25時間。放っておくと少しずつずれていき、夜型に傾きやすいのです。
さらに学校を休んでいると、日中は「みんなが勉強している時間」という罪悪感が大きく、夜のほうが気持ちが落ち着きやすい子が多いのです。
無理に戻さなくても大丈夫
「早く元に戻さなきゃ」と思いがちですが、無理に朝型に直すよりも、まずは 食事のリズム を合わせることからで十分。
起きた時間に合わせて「軽食→主食→タンパク質」を意識すると、体の時計が少しずつ整ってきます。
フルタイムで働くワーママにとって、「栄養価の高い手作りを」という思いがあっても、現実はそこまで手が回らない・・・。
私もそうです。
なので、色々と便利なものを活用しています。
▼ 勉強の不安との付き合い方
わが家の体験から
正直いちばん不安だったのは「勉強の遅れ」でした。
私はつい、「ゲームやYouTubeをやめさせれば勉強するんじゃないか」と思い、
「今日はドリルだけでも」「プリント1枚はやって」と声をかけたこともあります。
けれど、子どもは机に向かうどころか、ますます顔が曇っていきました。
「勉強=親に言われて嫌々やるもの」という空気になり、親子関係までギクシャク…。
そのときは本当に焦って、「このままずっと遅れたままじゃないか」と夜眠れないこともありました。
「取り戻せる」という言葉に救われた
そんな私を支えてくれたのが、不登校ジャーナリスト石井しこうさんの著書にあった一文です。
「義務教育の9年分の学びを取り戻すのに、9年もかかるわけではありません。本人に学ぶ意欲があり、健康なら、だいたい1年くらいで取り戻せるものです。」
(出典:婦人公論HPより)
この言葉を読んだとき、「遅れても大丈夫」と心がふっと軽くなりました。
「今は回復が先。勉強はその後でいい」と腹落ちした瞬間、子どもへの声かけも変わっていきました。
数年前に比べて、不登校の人数が増えてきています。
そんな中色々なサポートも増えているし、塾も「不登校に対応」としているところも増えてきました。
関連記事:「不登校はどれくらい増えているの?」
選択肢も増えた今、目の前にいる「我が子」に何が一番大切かを考える保護者が増えています。
▼浮き輪を手放す日は自然にくる
別の興味が芽生えるとき
ゲームや夜型生活は、子どもにとって「安心の浮き輪」です。
でも、心が落ち着いてくると、自然と別の興味を見つけることがあります。
実際に、わが家の子もある日「朝5時に起きて外に行きたい」と言い出し、散歩や自然観察に夢中になった時期がありました。
親が無理に“正しい生活”へ戻すより、本人の好奇心に寄り添うことのほうが回復を早めるのだと実感しました。
▼まとめ
昼夜逆転や勉強の遅れは、不登校の子が通る“自然なプロセス”。
焦って直そうとするよりも、安心を優先することが回復への近道です。
- 昼夜逆転は通過点ととらえる(まずは食事リズムから)
- 勉強は取り戻せると知り、焦らない
- 子どもの好奇心が出てきたらチャンスととらえる
ゲームも生活リズムも、「浮き輪」の役割を果たす時期があります。
やがて子どもは、自分の力でその浮き輪を手放し、新しい世界へ泳ぎ出していきます。
▼クロージング
子どもが安心を取り戻す道のりは、一気にではなく、ゆっくり少しずつ。
親が“がんばらせる”のを手放した分だけ、子どもは自分のペースで立ち上がる力を育てていきます。
今日も小さな変化を見つけて、静かに喜んでいきましょう。

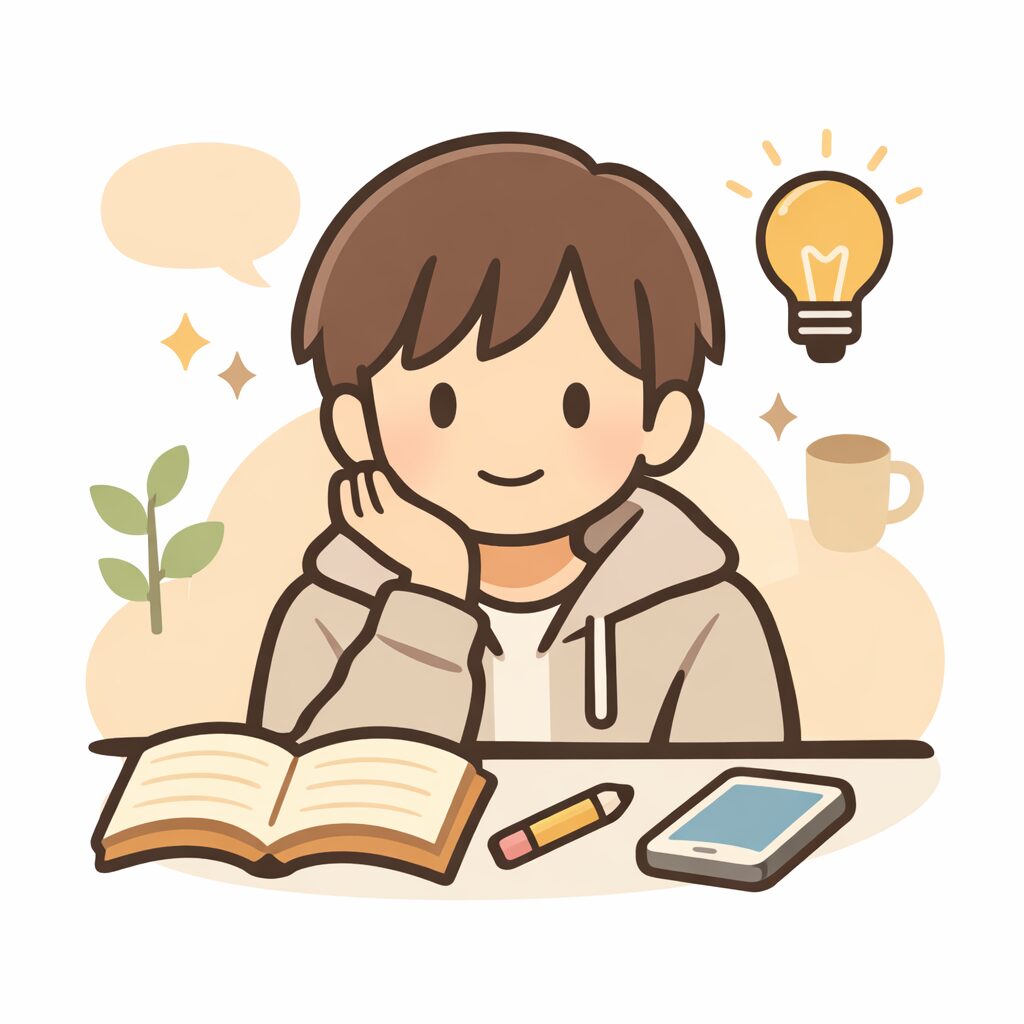


コメント