不登校の子どもを持つ親にとって、「自己肯定感が下がってしまうのでは…」という心配はとても大きなものです。
「学校に行けない自分はダメだ」と思い込んでしまう子も少なくありません。
けれど、実は家庭での声かけや日々の習慣によって、子どもの自己肯定感は少しずつ回復していく力を持っています。そしてその自己肯定感が、子どもの才能を伸ばす大切な土台になるのです。
海外に目を向けると、子どもの自己肯定感を育てることが教育の中心に置かれており、学力以上に「自分を信じる力」を重視している国もあります。
この記事では、フィンランド・アメリカの取り組みを紹介しながら、日本の状況と比べて見えてくる違いを整理します。
そして不登校の子どもを支える親が、日常生活に取り入れられるヒントをまとめます。
▼不登校と自己肯定感の関係
なぜ不登校で自己肯定感が下がるのか
学校はどうしても「出席できているか」「成績はどうか」で評価される場です。
その場に行けないこと自体が「できていない」「周りと違う」という劣等感につながりやすく、自己肯定感を大きく揺さぶります。
成績や出席で評価されないことの影響
特に日本では「皆勤賞」や「テストの点数」が重視される文化があります。
不登校の子どもは「どれも手に入らない自分」と感じてしまい、「自分の価値は学力や出席で決まる」という思い込みを強めがちです。
周囲からの視線と親の不安
さらに親の「心配」や「焦り」が子どもに伝わると、「迷惑をかけている」と思い込んでしまいます。
その結果、「どうせ自分なんて…」という自己否定につながることもあるのです。
▼フィンランド ― テストより自己肯定感を大切にする教育
「教育先進国」として知られるフィンランドでは、自己肯定感を育てることが学校教育の根幹にあります。
全国統一テストがほとんどない
フィンランドでは小中学校で全国一斉の学力テストはほとんどありません。
子どもたちを「順位」で並べるのではなく、一人ひとりの学びの過程を尊重するスタイルです。
教師は「結果」より「プロセス」を評価
テストの点数だけではなく、「どう学んだか」「どんな工夫をしたか」を評価の対象としています。
そのため、勉強が得意でない子も「努力したこと」「挑戦したこと」がきちんと認められます。
子どもの声を尊重する文化
授業中も「先生の話を黙って聞く」だけではなく、生徒の意見や感情を共有する時間があります。
「自分の考えを伝えてもいい」「間違えても大丈夫」という雰囲気が、安心感と自己肯定感を育てるのです。
👉 効果:評価のプレッシャーが少ないため、「自分はできない」という思い込みが減り、子どもが自分の存在に自信を持ちやすくなります。
▼アメリカ ― SEL(社会性と情動の学習)の導入
アメリカでは学力科目だけでなく、感情や人間関係を扱う教育「SEL(Social Emotional Learning)」が注目されています。
感情を学ぶ授業
SELの授業では「自分の気持ちを言葉にする」「相手の立場を想像する」といった練習を行います。
怒りや不安をどう扱うかを学ぶことは、不登校や問題行動の予防にもつながります。
人との関わりを重視
ディスカッションやグループ活動を通じて「協力する」「違う考えを尊重する」ことを体験します。
その結果、人との関係を築きやすくなり、学校生活への安心感が増します。
学校全体で取り組む姿勢
SELは一部の授業だけではなく、学校全体の文化として根付いています。
先生自身も「感情の扱い方」を学び、子どもの声を受け止める態度を大切にしています。
👉 効果:自己理解が深まり、仲間との関係も築きやすくなることで「自分はここにいていい」という実感が得られます。
▼日本との違いと見えてくる課題
日本の現状
日本では、学力や出席日数が依然として重視されます。
文部科学省の調査でも、日本の子どもは国際比較で「自己肯定感が低い」という結果が出ています。
「私は価値のある人間だと思う」と答えた日本の中学生は、調査国の中で最も低い割合でした。
海外との違い
- フィンランド:学力評価よりも「安心して学べる環境」を保障
- アメリカ:学力+感情教育(SEL)で「心の力」を重視
- 日本:依然として「成績や出席」で子どもの価値が判断されやすい
この違いは、不登校の子どもの自己肯定感にも大きく影響します。
「学校に行けない=価値がない」と思いやすいのは、日本独自の構造とも言えるでしょう。

▼才能を見つけることが自己肯定感につながる
小さな「できた」を見つけて伝える
「ごはんをよそってくれた」「妹に声をかけた」など、日常の小さな行動に「ありがとう」を添える。
👉 効果:行動そのものを認められると「自分は役に立っている」と感じ、自己肯定感が回復しやすくなります。
好きなことに没頭できる時間を肯定する
ゲームや絵を描く時間も「無駄」ではなく、「集中力や創造力を育てる才能の時間」として受け止める。
👉 効果:好きなことを尊重されると「自分の存在が認められている」と感じられ、自己表現力の芽が育ちます。
「比較」ではなく「気づき」で認める
「友達より遅いね」ではなく「やさしいね」「気づいてありがとう」と声をかける。
👉 効果:比較ではなく気づきを伝えることで「自分はそのままで大切にされている」と実感できます。
▼不登校支援へのヒント
海外の事例は、日本の不登校支援にも活かせます。
1. 学力にこだわりすぎない
フィンランドのように「点数」や「順位」で子どもを見ないこと。
「できた/できない」ではなく「どこまで取り組んだか」「どんな工夫をしたか」を認めてあげることが自己肯定感を守ります。
2. 感情や個性を尊重する
アメリカのSELのように、感情を言葉にする練習や「違っていていい」という体験を家庭で取り入れる。
「今日はどうしたい?」と聞いて子どもの気持ちを尊重するだけでも効果があります。
3. 家庭が安心できる場になる
学校で安心できない子どもにとって、家庭が「安全基地」になることは何よりの支えです。
「ここにいていい」と感じられることで、外の世界に出る力も少しずつ育ちます。
まとめ:世界から学ぶ、自己肯定感の育て方
海外の教育事例を見てもわかるように、自己肯定感は「学力よりもずっと大事な土台」として扱われています。
- フィンランドでは「評価のプレッシャーが少ない」教育で安心を保障
- アメリカでは「感情教育(SEL)」で自己理解と人間関係を重視
- 日本は「成績・出席」中心で、子どもの自己肯定感が低くなりやすい
不登校の子どもにとっても、学校に行けるかどうか以上に「自分を信じられる力」が未来を切り拓くカギになります。
家庭でできるのは、海外の取り組みと同じく「安心できる環境」と「自己肯定感を支える声かけ」。
世界の事例をヒントに、子どもの隠れた才能を信じて育てていきましょう。
▼関連記事
教育費どうする?シリーズ
- 【教育資金】学資保険より貯金+投資?インフレ時代の賢い準備法
- 【教育費どうする?②】教育無償化とは?制度を知って家計の負担を軽くしよう
- 【不登校はお金がかかる】少額から安心!SBI・SCHDで高配当投資デビュー
不登校シリーズ
- 【不登校×才能】学校では評価されない隠れた力をどう伸ばす?
- 【不登校×才能】海外の教育に学ぶ!自己肯定感を育てる3つの取り組み ←今回の記事
- 【最新データ】不登校はどれくらい増えてる?小中学生の現実
子育て✖ライフハック
- 宅配食材レビュー:ヨシケイで叶える時短ごはん
- 【不登校とゲーム】禁止せず安心を育てる3ステップ
- 【不登校】担任の先生への伝え方|親が知っておくべき学校対応の現実
- 【不登校と勉強不安】昼夜逆転も安心に変える3つの工夫

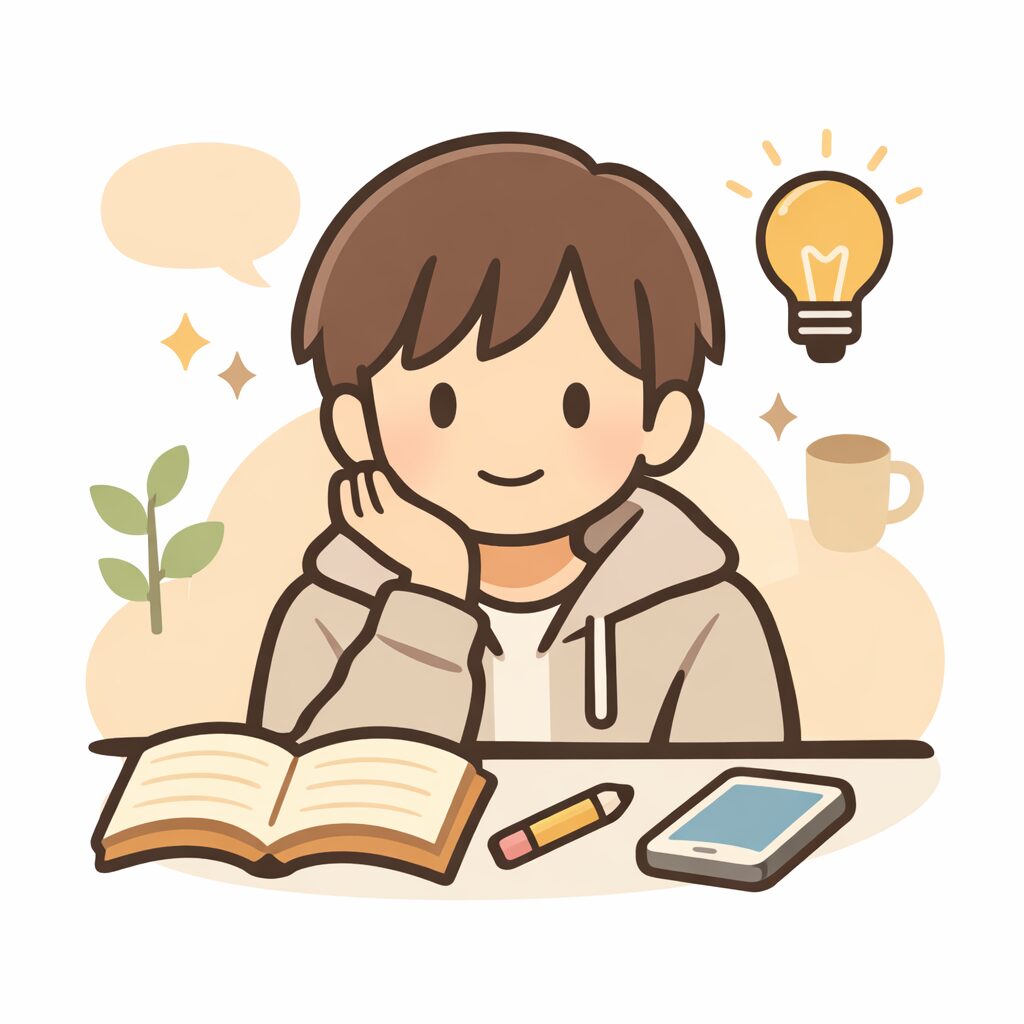


コメント