「うちの子、やりたいことが見つからない」「なんでも“別に”で終わってしまう」「学校に行きたくない」──そんな悩みを抱えていませんか?
実は、“やりたいことがない”子なんてほとんどいません。
ただ、“やってみたい”と思った瞬間を、周りの大人が見逃してしまっているだけかもしれません。
この記事では、不登校や登校しぶりのあるお子さんでもできる、
「やりたいこと」と「自由に選ぶ力」を育てる関わり方、
そして、親が陥りがちな“見返りの心理”をやわらげる方法を紹介します。
「やりたいことがない」は本当?
「うちの子、やりたいことがなくて…」
そう話す親御さんは少なくありません。
でも、“やりたいことがない”のではなく、
“やってみたい”が見逃されているだけかもしれません。
「どうせできない」
「やっても怒られる」
「途中でやめたら笑われるかも」
そんな思いが先に立って、心を閉ざしている子も多いのです。
親が「早く見つけなきゃ」と焦ると、
その“焦りの空気”が、子どもの芽をつぶしてしまうことがあります。
「夢を見つけさせよう」としていた私
私も以前はそうでした。
「将来困るよ」「得意なことを見つけようよ」と、
つい娘にプレッシャーをかけていました。
ある日、娘が静かに聞き返したんです。
「夢って、見つけなきゃいけないの?」
ハッとしました。
私は“夢を持たせよう”としていたけれど、
大事なのは“興味の芽をつぶさないこと”だったのです。
夢はどこかに落ちているものではなく、
「これ、楽しいかも」と感じた瞬間を少しずつ育てていくもの。
そこに気づいた瞬間、子どもとの関係が少し変わりました。
キッチンからはじまった「やってみたい」
娘の“やってみたい”は、お菓子作りから始まりました。
ホットケーキミックスをぐるぐる混ぜて、
キッチンを粉だらけにした娘を見て、
思わず「片づけてからにして!」と言いかけました。
でも、ふと手を止めてこう思ったんです。
「これも“やってみたい”の一歩なんだ」
そこで「今度、一緒にクッキー作ろっか」と声をかけると、
娘の顔がぱっと明るくなりました。
それから少しずつレシピを調べたり、道具をそろえたり。
気づけば、キッチンが“学びの場所”になっていました。
“やってみたい”という気持ちは小さな火のようなもの。
強く吹けば消えてしまうけれど、
そっと風を送れば、いつか自分の力で燃え上がります。
🌱家庭でできる「やってみたい」を育てる5つのコツ
1️⃣ すぐに「どうせ無理」と言わない
小さな挑戦ほど、応援の言葉を。
2️⃣ 結果よりプロセスをほめる
「よく考えたね」「工夫したね」と、過程を認めてあげましょう。
3️⃣ 親の価値観を押しつけない
「勉強になるか」ではなく、「ワクワクするか」で判断。
4️⃣ 環境を少し整える
材料をそろえる、時間を確保する、道具を貸す。
その小さな準備が「やってみよう」の背中を押します。
5️⃣ 興味が変わっても責めない
やめるのも成長。変化は“次の芽”のサインです。
「行きたくない」と言われた朝
「今日は行きたくない」と言われたとき、どう答えますか?
私は以前、つい「行きなさい」と言っていました。
でも、娘が泣きながら言った一言が胸に刺さりました。
「どっちにしても怒られる。」
“行かせること”が愛情だと思っていたけれど、
本当の愛情は、“選ぶ自由”を認めることだったんです。
「どうしたい?」と聞くだけで変わる
翌日から、私は質問を変えました。
「今日はどうしたい?」
行く・行かないだけでなく、
「寝たい」「家で勉強したい」「ゲームしたい」でもOK。
どんな答えでも「そう思ったんだね」と受け止めました。
すると数日後、娘が言ったんです。
「今日は自分で決めて、行ってみる。」
その瞬間、はっきりと気づきました。
“自由に選ぶ力”とは、他人に委ねない勇気のことなんだと。
🌿家庭でできる「選ぶ力」を育てる5つのヒント
1️⃣ 朝の服を自分で選ばせる
失敗してもOK。「今日はそれが着たかったんだね」と受け止めて。
2️⃣ ごはんのメニューを一緒に決める
「どっちがいい?」を日常会話に。
3️⃣ 休む・頑張るを自分で決める
「今日はゆっくりしたい」を尊重することで、自己調整力が育ちます。
4️⃣ “どうする?”より“どうしたい?”と聞く
正解を探す質問ではなく、“気持ちを軸にした選択”を促す。
5️⃣ 失敗したときは責めずに振り返る
「どうしてそう思ったの?」と穏やかに問いかければ、経験が学びに変わります。
「やりたい」と「自由」はつながっている
“やりたい”を見守ることと、“自由に選ぶこと”は、実は同じ根っこを持っています。
どちらも「自分の気持ちを信じて動く力」。
親が“挑戦を見守る勇気”と“自由を与える覚悟”を持つとき、
子どもは安心して、自分の人生を歩き始めます。
🌼それでも、つい「見返り」を求めてしまうとき
「これだけ我慢して、努力して、理解しているのに…」
そんな気持ちが湧くこと、ありませんか?
それは、愛が足りないからではなく、愛が深いからこそなんです。
「子どもが変われば、私の愛情は正解だった」と信じたい。
その優しさが、時に“成果型の愛し方”にすり替わってしまうだけ。
🌸見返りを手放す練習ワーク(親の実践編)
① ノートに「今日できたこと」を3つ書く
子どもの変化ではなく、自分の行動に焦点をあてて。
- 怒らずに話を聞けた
- 「どうしたい?」と聞けた
- 今日は笑顔で見送れた
書くことで、「私、ちゃんとやれてる」と実感できます。
スマホのメモ📝機能なども活用してみてください。気軽にできるし、日付も自動で入ります。
② 「関係の温度」を記録する
子どもがどう変わったかより、関係の温度を感じましょう。
- 一緒にお茶を飲んだ
- 目が合って笑った
- 無言でも同じ空間にいられた
「変化がなくても、つながっている」と知ることが、安心につながります。
③ 「期待」を書いて、ひと呼吸おく
「こうなってほしい」「こうしてほしい」と思ったら紙に書く。
そして、深呼吸してこうつぶやきます。
「これは私の期待。あの子のペースとは違うかもしれない。」
そう意識するだけで、“期待”と“信頼”を分けて持てるようになります。
💭まとめ:「見返りを求める私」も、ちゃんと愛している
子どもが笑わなくても、前に進めなくても、
あなたが今日も向き合おうとしたこと──それが、すでに愛です。
「私は、ちゃんと愛してる」
「この愛は、結果のためじゃなく、関係のためにある」
そう思えたとき、
見返りのループからふっと抜け出せて、
子どもも少しずつ、自分の足で歩きはじめます。
焦らず、見守る勇気を。
今日から、あなたの家庭が“安心して挑戦できる場所”になりますように。
- 🎍年末年始、三世代10人で沖縄へ✈️
- 【ワーママ副業】楽天ROOM9月→12月で変わったこと
- 【勉強しない】うちの子が、実は静かに“伸びていた”理由
- 【不登校×やりたいを育てる】“やりたいことがない”は嘘かも?自由と見返りを手放す家庭のつくり方
- 【共感×自己理解】泣く・怒る・黙る・・・不登校の我が子の心をひらく聞き方と感情の整え方

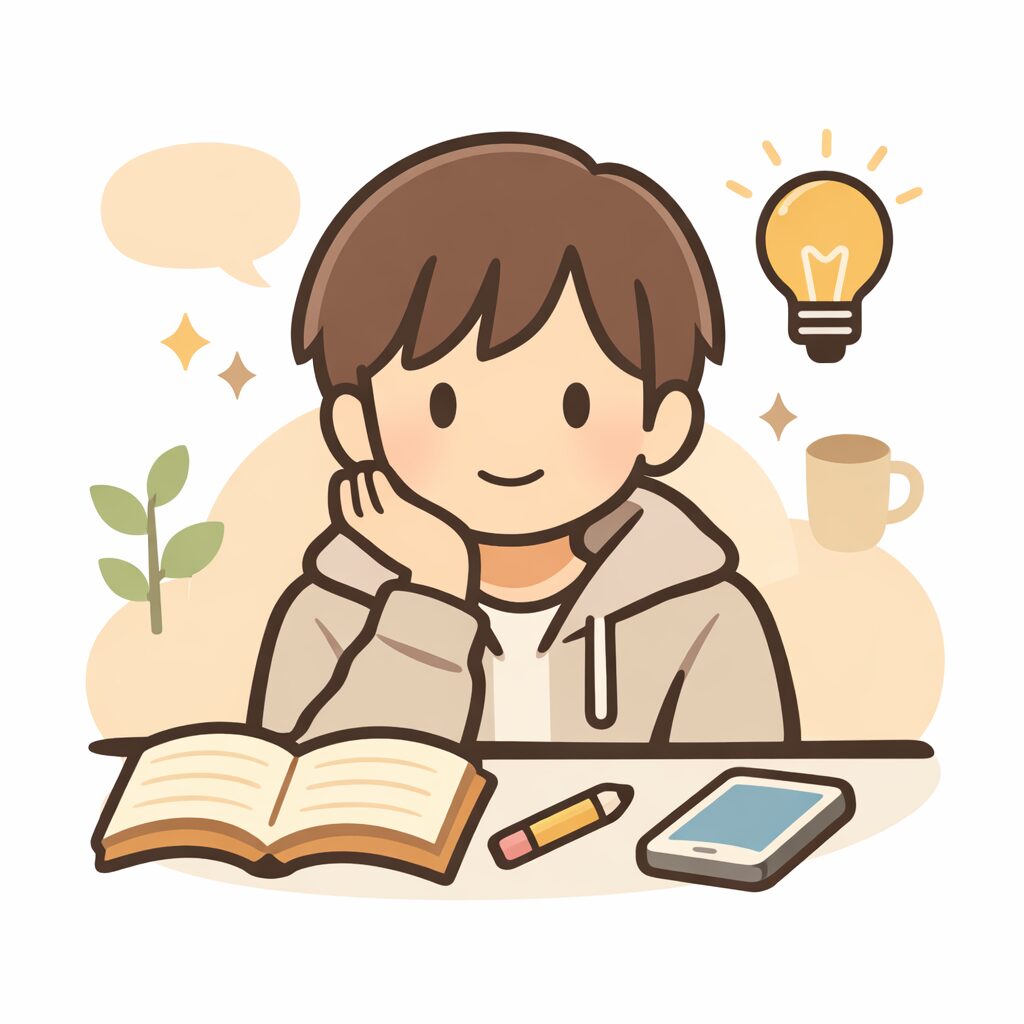


コメント