40代になると、家の中にどんどん物があふれてきます。
子どもが3人いれば、おもちゃや洋服、学校からのプリントや作品…。さらに夫婦の物も合わせると、収納スペースはすぐに限界に。
私自身、最初は「メルカリで売ればいい!」と挑戦しました。最初は売れて楽しかったのですが、途中から売れなくなり、段ボールだけが増える結果に…。最近は「思い切って手放す」フェーズに入りました。
さらに我が家には、ADHDの特性をもつ次女がいます。
整理整頓が苦手で、物が多いと気が散りやすく、不安定になりがち。だからこそ、
暮らしやすい環境=シンプルでわかりやすい仕組みを作ることが欠かせません。
ADHD児がいる家庭の片づけの壁
ADHDの子どもにとって片づけが難しいのは「努力不足」ではなく「脳の特性」が理由です。
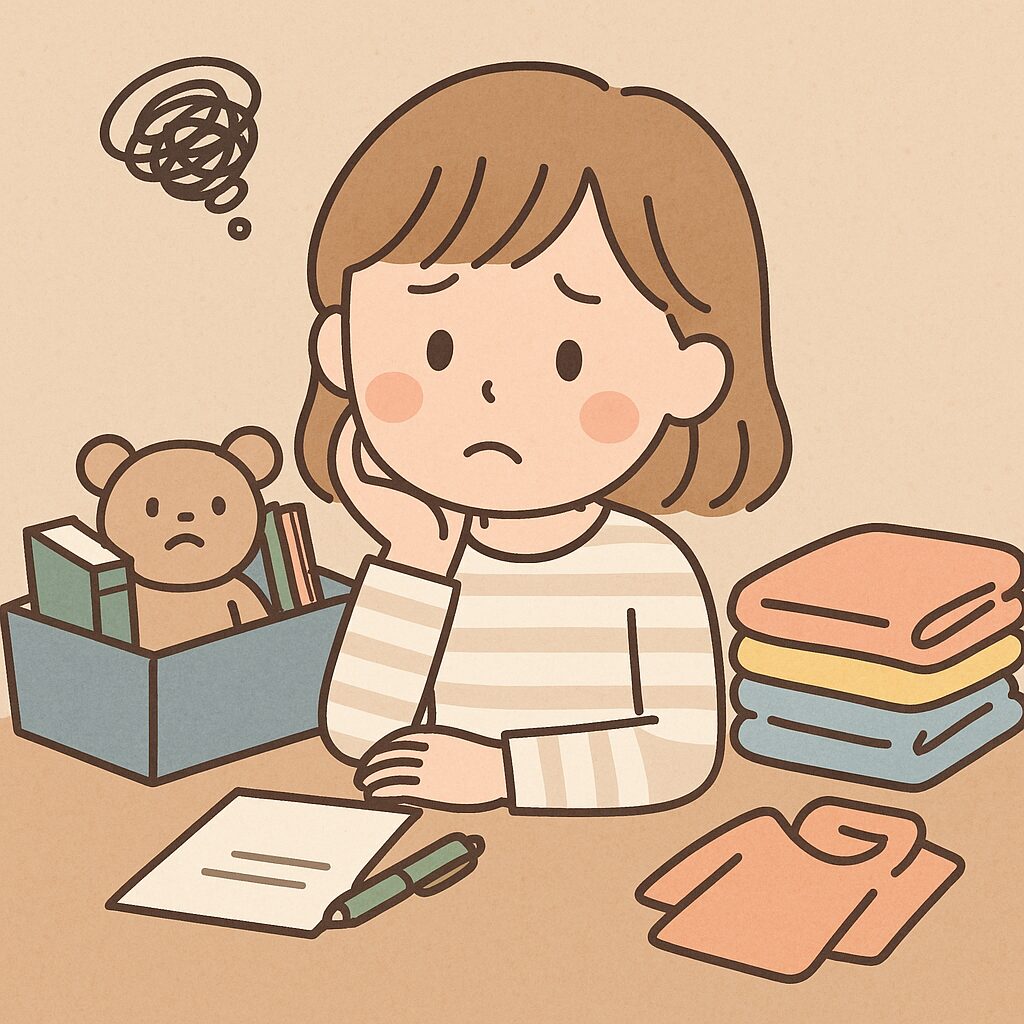
✅ どこに戻すか覚えるのが苦手
✅ 手順通りに続けるのが難しい
✅ 物が視界にあると気が散ってしまう
だから、親が「ちゃんと片づけなさい!」と声をかけても、なかなか進まないのは自然なこと。
ここを理解してあげることが、安心感につながります。
ADHDフレンドリーってなに?
私がよく使う言葉に「ADHDフレンドリー」というものがあります。
フレンドリー=やさしい、負担が少ない、という意味で、
ADHDの特性に合わせた“やさしい仕組みづくり” を指しています。

ADHDの子に「ちゃんと片づけなさい!」と言ってもなかなか進まないのは、努力不足ではなく「脳の特性」が理由。
計画・記憶・注意をコントロールする「実行機能」が苦手だからです。
だから大切なのは、
- ✅「頑張ればできる」ではなく
- ✅「頑張らなくてもできる仕組み」を用意すること。
これが私のいう「ADHDフレンドリーな断捨離」の考え方です。
子どもと一緒にできる断捨離の工夫
我が家が取り入れている工夫は「がんばらなくても続けられる仕組み」です。
① ラベルで“外部化”
半透明ボックスに「文字+イラスト」のラベルを貼る。
戻す場所を覚えなくても、自分で管理しやすくなります。
② ざっくり収納
小分けにしすぎない。フタなしケースにポイッと投げ入れるだけでOK。
「断捨離」的には、収納ケースを購入するのは❌とされています。
余計にものが増えるから・・・。
しかし、しかしです。
ADHDの子どもでも大人でも、「わかりやすさ」というのは、一番効果的な対策の一つです。
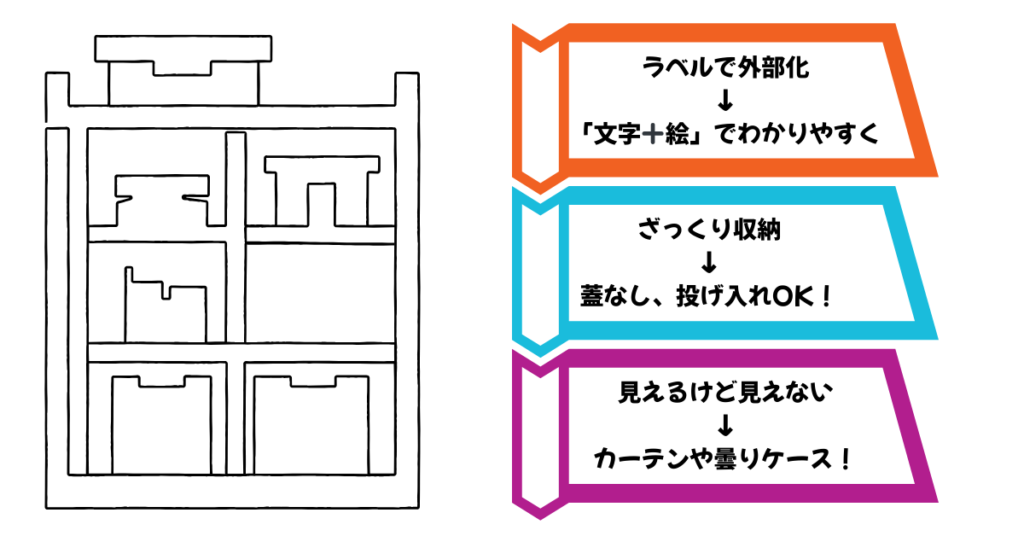
③ 見えるけど、見えすぎない
よく使う物は見える場所に置く。
ただし、部屋全体は布カーテンや曇りケースでごちゃごちゃを隠すと安心感が出ます。
①〜③を実行していくためには、「収納ケース」・・・購入した方がいい。
私は、ニトリで揃えました。無印もあるけど、少し割高だったのと、自宅からニトリの方が近いということで、ニトリで揃えることにしました。
④ 短時間リセット
「15分だけ」「机の上だけ」と時間と範囲を区切る。
短時間なら子どもも集中しやすい。
⑤ 家族で一斉片づけ
「よーいどん!」で不要な物を集める。
子どももゲーム感覚で楽しめて、一気に物が減ります。
まずはキッチンから始めてみよう

断捨離を始める場所に迷ったら、キッチンがおすすめです。
理由はシンプル。
- スペースが狭いので成果が出やすい
- 母(親)だけで完結できる
- 捨てる・残すの判断基準が比較的明確
例えば、
「賞味期限切れの調味料」や「使っていない保存容器」など、判断しやすいものから手をつけると、短時間でスッキリを実感できます。
親が先に経験するメリット
子どもに「断捨離しよう」と声をかける前に、まずは親が自分でやってみることが大切です。
- 成果が目に見えてわかる
- 自分も“捨てる葛藤”を経験できる
- 子どもが片づけに悩む気持ちが理解できる
「ママもやってるんだ」という姿を見せるだけで、子どもも自然と片づけに向き合いやすくなります。
メルカリ失敗談|捨てられない問題
断捨離をしようと思っても、頭をよぎるのが「これ、メルカリで売れるかも?」という気持ち。
最初の頃は出品すればすぐ売れて、ちょっとしたお小遣いにもなり楽しかったのですが…。

だんだん売れなくなり、
「売れるまで置いておこう」とクローゼットにため込む → 結果、余計にスペースを圧迫してしまいました。
結局、クローゼットは“売れるかもしれない物置き場”になってしまい、余計に散らかることに。
子どもの物も「まだ使える?」で止まる
子どもの物は特に判断が難しいですよね。
服やおもちゃ、学用品などを手に取っては、
- 「まだ使えるかも?」
- 「妹が使うかもしれない」
- 「思い出があるから捨てにくい」
と、なかなか手放せません。
でも、実際はそのまま置いておいても使わないことが多いんです。
「本当に必要?」と自分に問いかけて、思い切って手放す勇気も大切だと感じています。
攻め時と引き時も大切
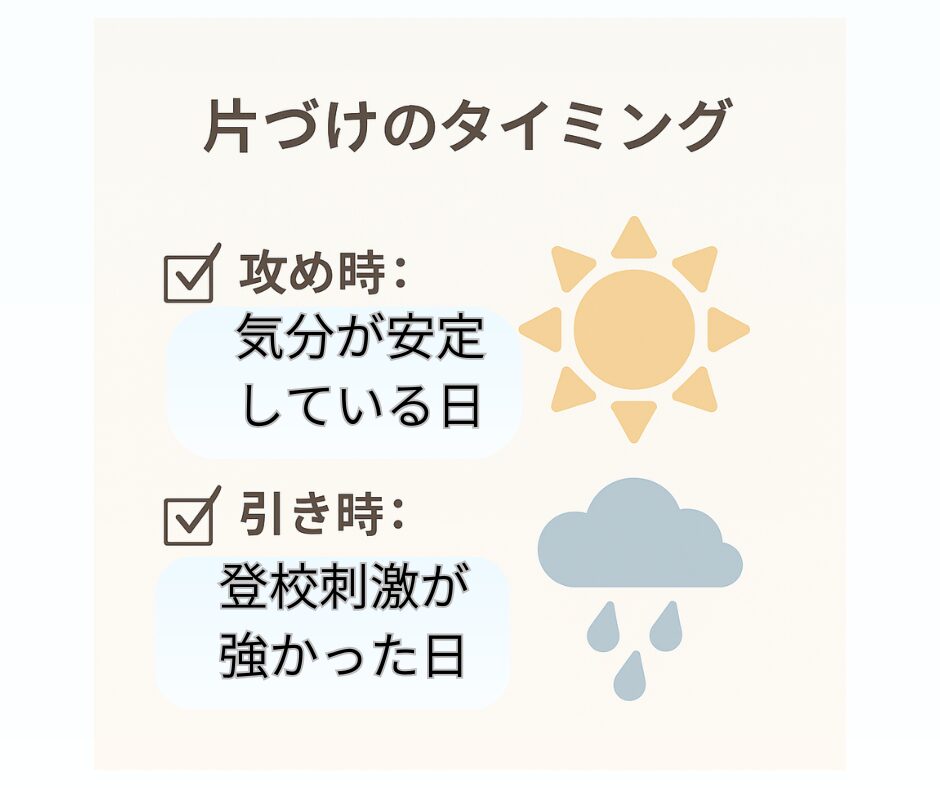
- 攻め時:子どもの体調や気分が安定している日
- 引き時:登校刺激が強かった日、病院や面談のあと、疲れているとき
片づけよりも「安心」を優先することが鉄則です。
ADHD家庭で避けたい片づけNG行動
✅ 無断で捨てる(特に作品やコレクションは信頼関係を壊す原因に)
✅ 細かすぎる分類で“戻すのが面倒”になる
✅ 透明収納ばかりで視覚がごちゃごちゃする
まとめ|小さな成功体験を積み重ねよう
不登校やADHDの子がいる家庭では、片づけを「根性」でやり切ることはできません。
- 親子で一緒にゲーム感覚で取り組む
- 工程は少なくする
- “迷う”を許す仕組みをつくる
この3つを意識するだけで、家も心もグッとラクになります。
完璧を目指さなくても大丈夫。
「今日はテーブルの紙をゼロにした」
「ゴミ袋ひとつ出せた」
そんな小さな一歩が、暮らしと心を少しずつ軽くしてくれますよ🌱
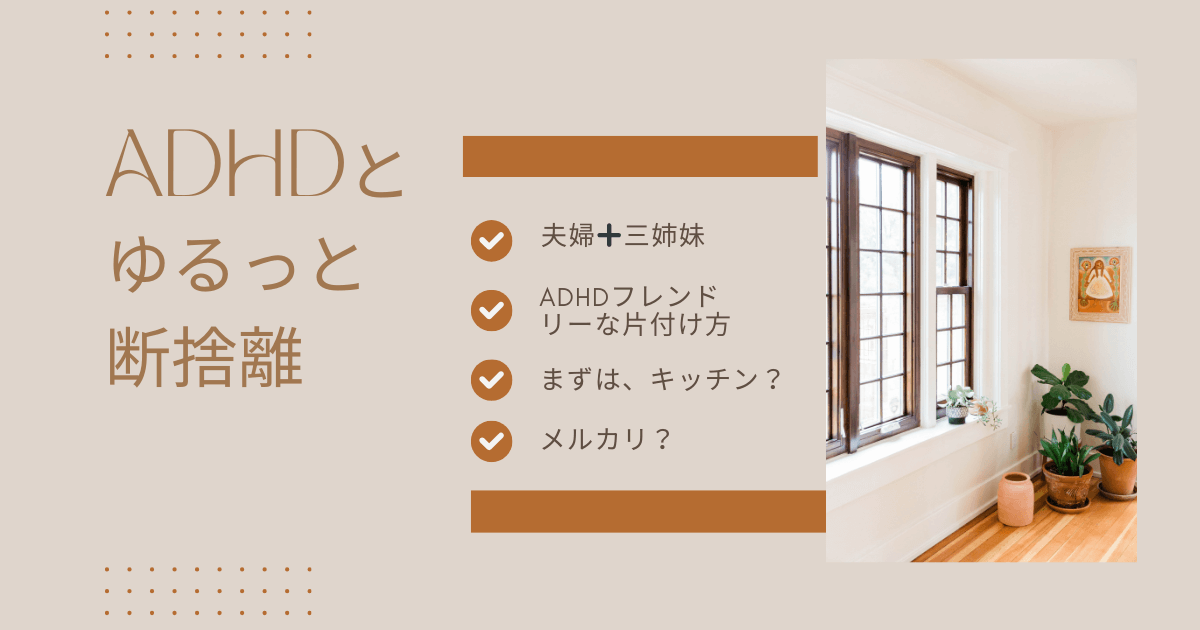
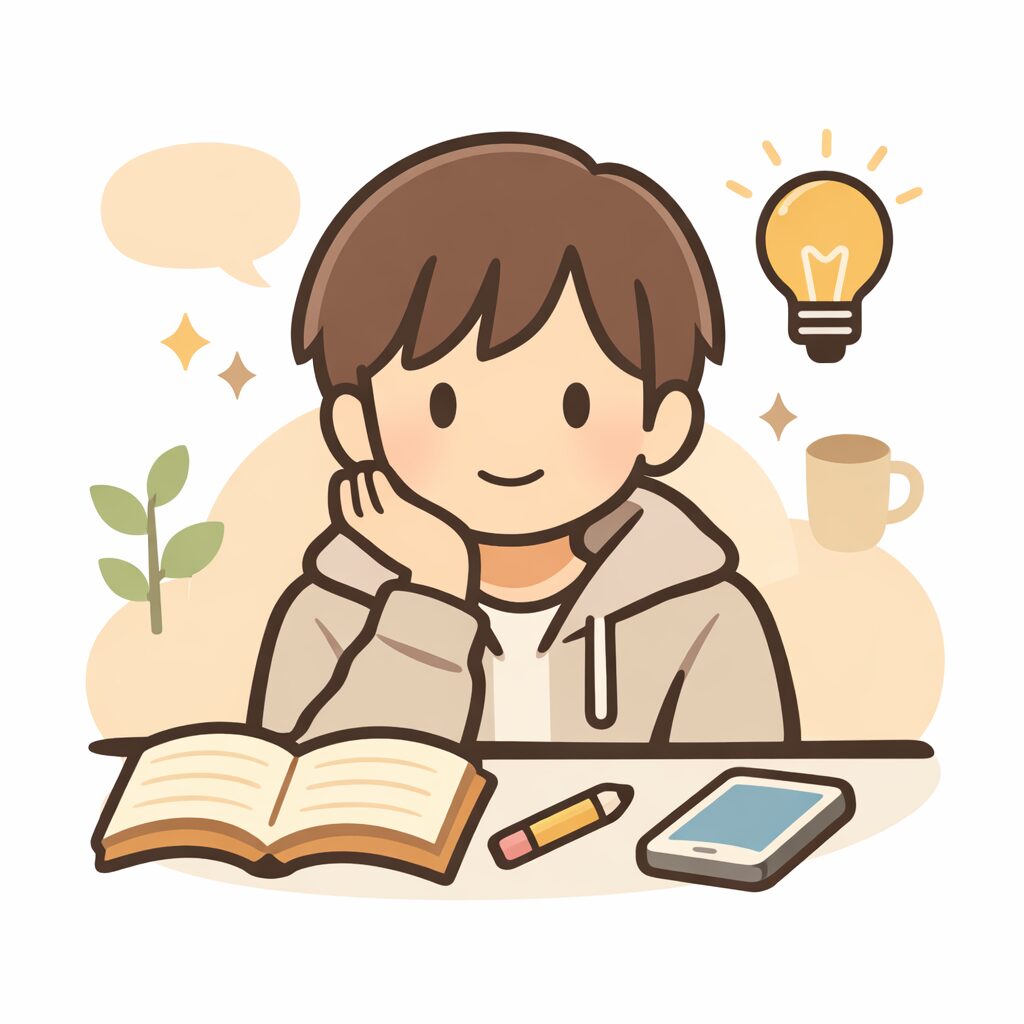


コメント