学校を休みがち…「どうしたらいいの?」
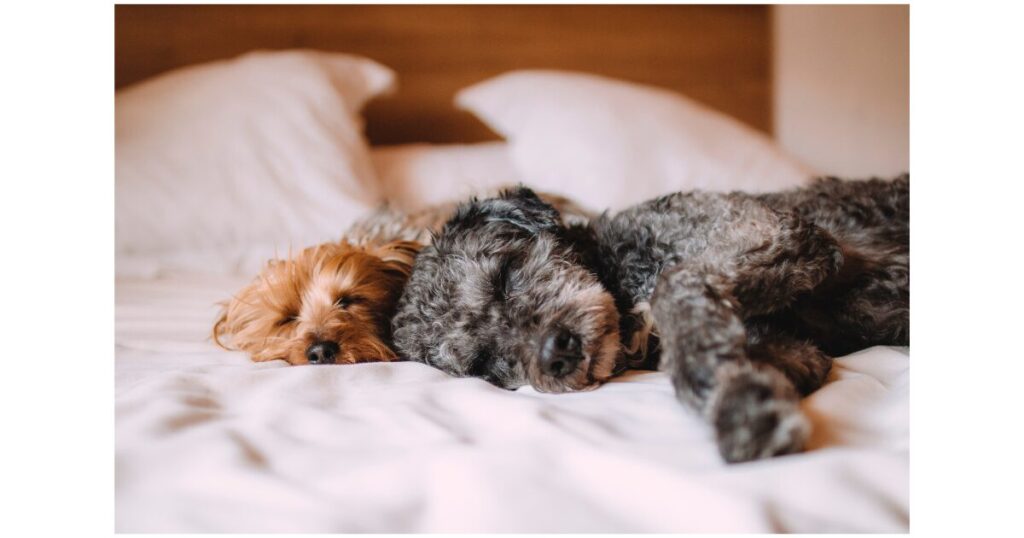
「昨日も休んだのに、今日も『行きたくない』って言われた…」
そんなとき、親としては焦ったり、つい「無理にでも行かせないと」と思ってしまいますよね。でも、休みが続き始めたときこそ、落ち着いて子どもの気持ちを受けとめることが大切です。
「このまま不登校になってしまうのでは?」「将来は大丈夫?」と不安が膨らみ、つい強い言葉をかけてしまうこともあると思います。
でも、子どもが「行けない」と言葉に出せていること自体が、心のSOSのサイン。最初に大切なのは、“解決すること”よりも“受けとめること”なんです。
まずは「安心できる環境」をつくる
学校に行けない日があっても、家の中で安心して過ごせることが一番。
「行けない=ダメな子」ではなく、「今日はここで安心して過ごそうね」と声をかけるだけで、子どもの心はずいぶん楽になります。
「理由を聞きすぎない」も大事
「どうして行けないの?」と何度も聞いてしまうと、子どもはますます追い込まれてしまうことがあります。
理由を言葉にできないことも多いので、まずは「行けない気持ちがあるんだね」と受けとめてあげることが、信頼につながります。

ほんと、毎回追い詰めてしまいますよね・・・。
産んだ時から、ずっっっと育ててきていて、「急に」「まさか」など色々な負の感情が一気に溢れ出てきます。
そこで何度も問い詰めてしまうと、「分からない自分はダメなんだ」と自己否定につながってしまうんです。
大切なのは「行けない気持ちがあるんだね」と受けとめること。言葉にならない思いも尊重してあげましょう。すると、子どもは「ここなら安心して話せる」と感じ、自然に少しずつ心の内を伝えてくれるようになります。
学校との連絡はシンプルに
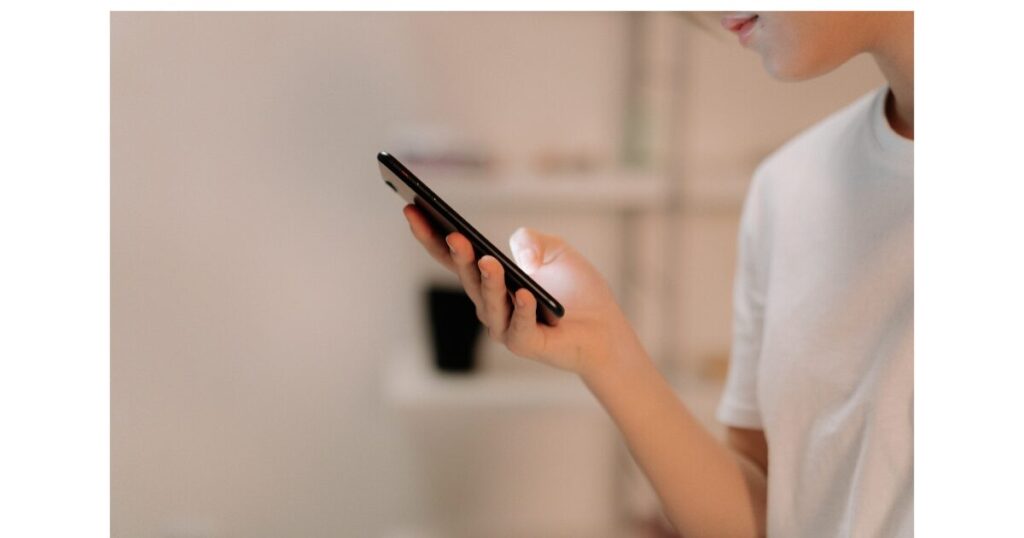
担任の先生へは「今日は休みます。体調は落ち着いています」など、シンプルな連絡で大丈夫です。
長文で事情を説明しようとすると、親自身も疲れてしまいます。
学校との詳しいやりとりは、もう少し落ち着いてからでも遅くありません。
もし先生から「詳しく聞かせてください」と言われても、「また改めてお話ししますね」と伝えればOK。今は子どもの安心が最優先です。
学校とのやり取りは、親が無理のない範囲で続けられる形にしていくのがポイントです。
最近は、先生側もしつこく問いただすことは激減しています。
なぜか・・・
不登校がある意味「普通」になってきているからです⬇️
それと、シンプルに「面倒なことになるのは嫌だから・・・」という心理が先生側にも働きます。
担任の先生も悩んでいます

実は、不登校の子どもを担任する先生も「どう接したらいいのだろう」と悩んでいます。
- 無理に登校させて逆効果にならないか
- 家庭にどう声をかけたらよいか
- 他の子とのバランスをどう取るか
先生も「何とかしてあげたい」という気持ちは強いのですが、正解が分からずに迷っていることも多いんです。
親と先生の気持ちは同じ方向を向いている
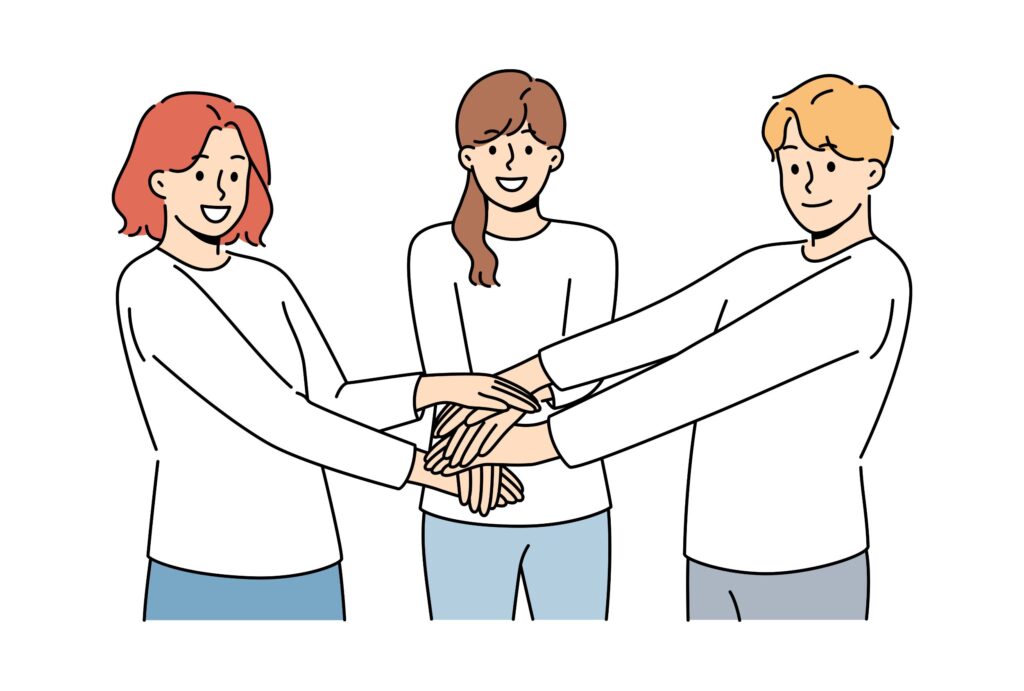
先生も親も「子どもが安心して過ごせるように」という思いは同じです。
だからこそ、先生に全部を話そうとせずとも「今は家庭でゆっくり過ごしています」と一言伝えるだけで十分。
そのやりとりが積み重なることで、先生も「見守っていて大丈夫だ」と安心し、子どもに無理な働きかけをしなくなります。
日常生活のリズムをゆるやかに整える
家にいる日が続くと、夜更かしや昼夜逆転になりがちです。
「ちゃんと起きなさい!」と厳しく言うよりも、「午前中に一度はカーテンを開けて、朝の光を浴びる」など、できることから少しずつ整えていくと子どもも取り組みやすいです。
生活のリズムが整うことで、心も少しずつ安定し、次の一歩につながります。
まとめ
子どもが休みがちになったときに親ができるのは、
- 家を安心できる居場所にすること
- 理由を追及しすぎないこと
- 学校への連絡は簡潔にすること
この3つを意識するだけで、子どもも親も少し楽になりますよ。
不登校のとき、親も先生も「正しい対応を探さなきゃ」と焦ります。
けれど大切なのは「子どもを安心させたい」という同じ願いを共有すること。
担任の気持ちをほんの少し知るだけで、親の肩の力もふっと抜けるはずです。
🌱次の記事では、学校とのやり取りで気をつけたいポイントを具体的にお伝えします。


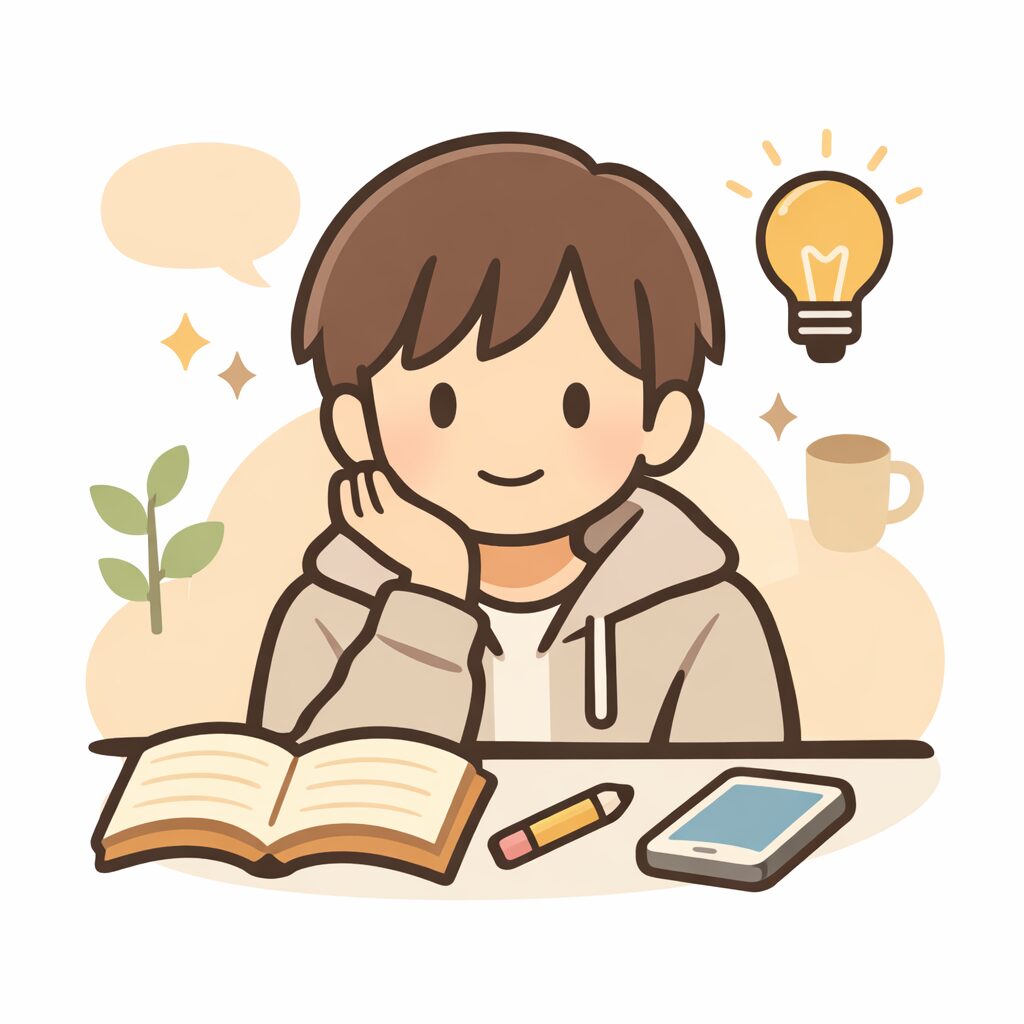

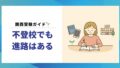
コメント