「うちの子、不登校で勉強が遅れてしまっている…」
そんなふうに不安を感じている親御さんは少なくありません。
けれど実は、学校に行けないことで「学力」だけに縛られない時間を過ごす中で、
非認知能力(学力では測れない力)が育つこともあります。
AIが知識や計算を簡単に代わりにやってくれる時代。
だからこそ「人の気持ちを理解する」「やり抜く」「共感する」といった力が、これからの社会で大切になっていきます。
この記事では、海外の研究、日本のデータ、そしてわが家の体験を交えて、不登校の子どもが持つ「隠れた才能」と、その伸ばし方を紹介します。
▼認知能力と非認知能力の違い
まずは整理から。
- 認知能力:学力テストで測れる力。暗記、計算、論理思考など。
- 非認知能力:気持ちをコントロールする力、粘り強さ、協調性、共感力、創造力など「心の力」。
これまで学校では主に「認知能力=学力」で評価されてきました。でも今はAIが知識や処理を代替する時代。人間にしかできない非認知能力の価値がどんどん高まっています。
そう、認知能力を持っているだけでは十分でない世界が近づいています。
ここで、コテンラジオでおなじみの深井龍之介さんが語る“歴史思考”の視点がヒントになるんです。
深井さんはこう言います。
『歴史を通じて “自分の認知の枠組み” を見つめ直すことで、物事を多面的に見る力=メタ認知能力が育つ』
実際、彼は経営が苦しくなったとき、歴史思考を使って考え方を更新することで乗り越えた経験も語っています。
認知能力を使って知識を得ることは大事。
でも、それだけに頼ると視野が狭くなる。龍之介さんの言葉を借りるなら、
「自分がどう考えているか」を意識できる力、つまりメタ認知的視点が、これからの時代を生きる上での“差”になるかもしれない。」
ということになりますね。
認知能力やメタ認知の重要性を理解すると、次に気づくのは「学校という枠の外にいる子が持つ強み」です。
不登校の子は、日常的に“多数派のルール”から離れて暮らすからこそ、他の子とは違う目線や感受性を育みやすい。
たとえば、人の気持ちを敏感に察する力、周囲をよく観察する力、ひとつのことに深く没頭する集中力…。これらはまさに非認知能力の芽であり、不登校という経験の中で形を帯びていく才能なのです。
「学校に行けていない=遅れている」と焦る気持ちは当然。
でも、実はその裏で、未来を支える力が少しずつ育っているかもしれません。
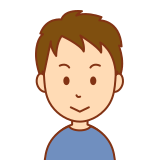
実は海外では、不登校や“学校に合わない子”が才能を開花させた事例がたくさんあるんです!少し見ていきましょう!
▼海外に学ぶ「才能を見つける視点」
- 『Quiet Power』(Susan Cain)
内向的な子は「観察力」「共感力」といった静かな強みを持つ。学校で目立たなくても、それは才能。 - 『The Element』(Ken Robinson)
学校で落ちこぼれ扱いだった子どもが、ダンスやITで才能を開花させた事例を紹介。「好き」と出会った瞬間に人生が変わる。 - 『Grit』(Angela Duckworth)
成功を決めるのは学力ではなく「情熱」と「やり抜く力」。
👉 不登校だからこそ、学校の枠から離れて「好き」「得意」に出会えるチャンスがあります。
▼日本の研究からわかること
- 尼崎市の調査(2024年)
協調性・勤勉性・精神の安定性が低い子ほど長期欠席になりやすい。
尼崎市教育委員会と研究者が共同で行った調査では、公立小中学校の児童・生徒約 5,000人規模 を対象に、非認知能力(ビッグファイブ:外向性・協調性・勤勉性・開放性・精神安定性)と長期欠席との関係を統計分析しました。
- 協調性が低い子は、長期欠席のリスクが1.4倍
- 勤勉性が低い子は、長期欠席のリスクが1.7倍
- 精神の安定性が低い子は、長期欠席のリスクが1.5倍
つまり「成績の高さ」よりも、気持ちや性格の安定が欠席に強く影響することが示されています。
- 国立教育政策研究所(2024年)
小中接続期の学校・家庭環境が、子どもの社会情緒的スキル(非認知能力)に強い影響を与える。
小中学校の接続期(小6→中1)の児童・生徒を追跡した調査では、約 2,500人 を対象に「社会情緒的スキル(非認知能力)」がどのように育つかを分析しました。
- 学校での安心感(先生や友達との関係)が高い子ほど、自己肯定感スコアが平均15%高い
- 家庭で「気持ちを受け止めてもらえている」と感じる子は、自己効力感(やればできると思える力)が平均20%高い
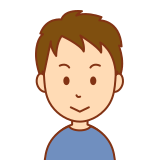
環境次第で非認知能力はぐんと伸びる、ということを示すデータです。
- SEL(社会性と情動の学習)実践校の報告
感情や人間関係の学びを取り入れた学校で、不登校改善や教員の休職ゼロといった成果。
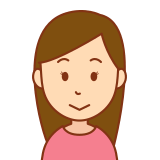
SELってそもそも何のことですか?
学校の先生にも影響があるみたいですが。
SEL(Social and Emotional Learning:社会性と情動の学習)とは、
子どもたちが以下のような力を身につけることを目的とした教育プログラムです。
- 自分の気持ちを理解する力(自己認識)
- 気持ちをコントロールする力(自己管理)
- 他者を理解し、思いやる力(社会的認識)
- 人と協力し合う力(対人関係スキル)
- よりよい判断や行動を選ぶ力(意思決定)
つまり、「勉強の力」だけではなく、生きるために必要な心の力や人間関係の力を育てる学びです。
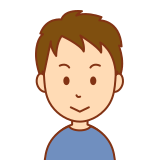
SELは「子どもに優しい教育法」だけではなく、先生や学校全体の環境改善にも効果があることが注目されています。
日本ではまだ取り入れ途上ですが、海外(アメリカや北欧)ではSELは広く導入されていて、学力向上やいじめ減少などの効果も示されています。
おまけ:海外の研究データ
SELの効果は国際的にも数多くの研究で裏付けられています。
代表的なものをいくつか紹介します。
1. 学力への効果
- アメリカでの大規模メタ分析(Durlak et al., 2011, 約27万人対象)
→ SELプログラムを受けた子どもは 学力が平均11ポイント向上。 - 単に「心の学び」ではなく、学習意欲や集中力アップがテスト成績にも反映。
2. 問題行動の減少
- 反社会的行動(いじめ・暴力行為)が 10%以上減少。
- 教室の規律が改善し、学級経営が安定。
3. 精神的健康の改善
- 不安や抑うつ傾向の子どもが 約16%減少。
- 自己肯定感やレジリエンス(困難を乗り越える力)が高まる。
4. 教師への効果
- 米国での報告(Jennings & Greenberg, 2009)
→ SELを取り入れた学校では、教師のストレスが軽減し、離職率も低下。
- 親の意識調査
9割以上の親が「学力だけでなく、非認知能力の育成も大事」と回答。
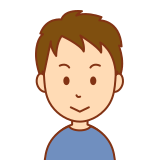
不登校の子を持つ親にとって「学力の遅れ」だけを不安に思う必要はありません。非認知能力こそが、将来の幸福や適応力に深く関わるのです。
▼わが家の体験を少し・・・
長女・さつまいもちゃんは、小学校の頃はそれなりに成績も安定していて、「このまま積み上げていけば大丈夫」と思っていました。ところが、中学に入ると状況は一変。成績はまるで滝のように下がっていき、私自身「えっ、あんなに頑張っていたのに?」と信じられない気持ちになりました。
塾に通わせる?家庭学習を増やす?いろいろな手を考えましたが、本人のやる気はどこか上の空。私が焦れば焦るほど、子どもとの間に距離ができていく感覚がありました。
そして迎えた高校進学のとき。担任や進路指導の先生からは「普通科に進んでおいたほうが大学進学の道は広い」と何度も言われました。でも、さつまいもちゃんが口にしたのは「情報科学科に行きたい」という言葉。ゲームやパソコンに関心があった彼女にとって、専門学科のほうが魅力的だったのです。
親としては正直、迷いました。
「専門学科って大学進学に弱いんじゃない?」
「将来の選択肢を狭めてしまわない?」
そんな思いが渦巻きました。
でも同時に、これまでの「積み上げが崩れていく経験」を見てきたからこそ、私は吹っ切れました。勉強は積み上げても、ちょっとしたきっかけで崩れることがある。ならば、本人の希望や適性に賭けたほうがいい。そう思い切ったのです。祖父母の反対も振り切りました。それが親として役目だと思ったからです。
いま振り返ると、あの決断は「不登校の子に寄り添う」ことと同じ方向を向いていました。つまり、親の理想や世間の価値観で選ぶのではなく、子どもの内側にあるものを信じるという姿勢です。
情報科学科で学んでいるさつまいもちゃんの姿は、確かに「学校の枠組み」では評価されにくかったけれど、彼女なりの才能を少しずつ形にしつつあるように見えます。
学校では常に上位に位置しています。あんなに勉強が嫌だったのに。今は、好きなプログラミングを中心に学習するので、彼女にとって「意味のある学び」が毎日繰り広げられていて、充実した毎日を過ごしています。

「高校がいちばん楽しいかも・・・」
この前ふと、さつまいもちゃんがそう呟いていました。 本人の幸せが一番ですね。
一方で、次女のアスパラちゃんはまだ小6。
不登校が続いていて、勉強の積み上げは正直あまりできていません。親としては心配になる瞬間もありますが、長女の経験を見てきたことで、少し気持ちが変わりました。
「成績が積み上がっていても、中学で一気に崩れることがある」
「逆に、不登校でも“人の気持ちを察する力”のような才能が育つこともある」
そう思えるようになったのです。
アスパラちゃんは、友達や家族のちょっとした表情の変化にすぐ気づきます。相手の心を考えて先回りして動ける優しさがあります。もちろん、その繊細さが裏目に出て、気を遣いすぎて疲れたり、爆発したりすることもあります。けれど、それもまた豊かな感受性の裏返し。
今はまだ形になっていなくても、将来きっと何かの場面で彼女の強みになると信じています。
▼家庭でできる「非認知能力」の育て方
- 感情を言葉にする練習:「今、悲しいんだね」と共感的に返す。
- 小さな挑戦と成功体験:料理を一緒に作る、ゲームを工夫する。
料理を一緒に作る、買い物で計算を任せる、家族旅行の計画を考えてもらうなど、日常の中で「ちょっと頑張ればできること」を任せてみる。
👉 失敗しても再挑戦し、成功すれば「できた!」という自信に。やり抜く力(グリット)が自然に育ちます。
でもママとしては、料理がモタモタ作られたり、材料を用意したりするのにストレスを感じることも少なくありません。私もそうです。
そんな時の関連記事:【宅食✖️不登校】の記事。栄養のことを気にして実践記録ですが、全部セットで届けてくれるので、心の余裕ができます。
働くあなたに簡単レシピでバランスごはんをお届け♪食材宅配のヨシケイ- 比較より気づきを大切に:「やさしいね」「気づいてありがとう」と言葉で伝える。
「お姉ちゃんより遅いね」ではなく、「やさしいね」「気づいてありがとう」と小さな行動をそのまま認めて言葉にする。
👉 親に認められた経験が「自分は役に立つ存在なんだ」という安心感を育て、自己肯定感が高まります。不登校で学校から評価されにくい子どもにとって、家庭が一番の安心できる居場所になります。
- 安心できる居場所を守る:無理に学校だけにこだわらず、家庭を安全基地に。
- 子どもの好きな本やゲーム、絵を飾れるスペースをつくる。
- 部屋の一角に「自分の安心ゾーン」を用意してあげる。
👉 自分の好きなものに囲まれることで「ここにいていい」と思えるようになり、ストレスが軽減する。
▼まとめ:不登校は才能を育てるチャンス
- 不登校の子には、観察力・共感力・感受性といった非認知能力が隠れている。
- 学力がAIに代替される時代、人にしかできない力がより価値を持つ。
- 親が「学力だけではない」と視点を変えると、子どもの可能性は大きく広がる。
不登校は決して「マイナス」ではなく、子どもの才能を見つけるチャンスです。
今日から少しずつ、わが子の「隠れた力」に目を向けてみませんか?
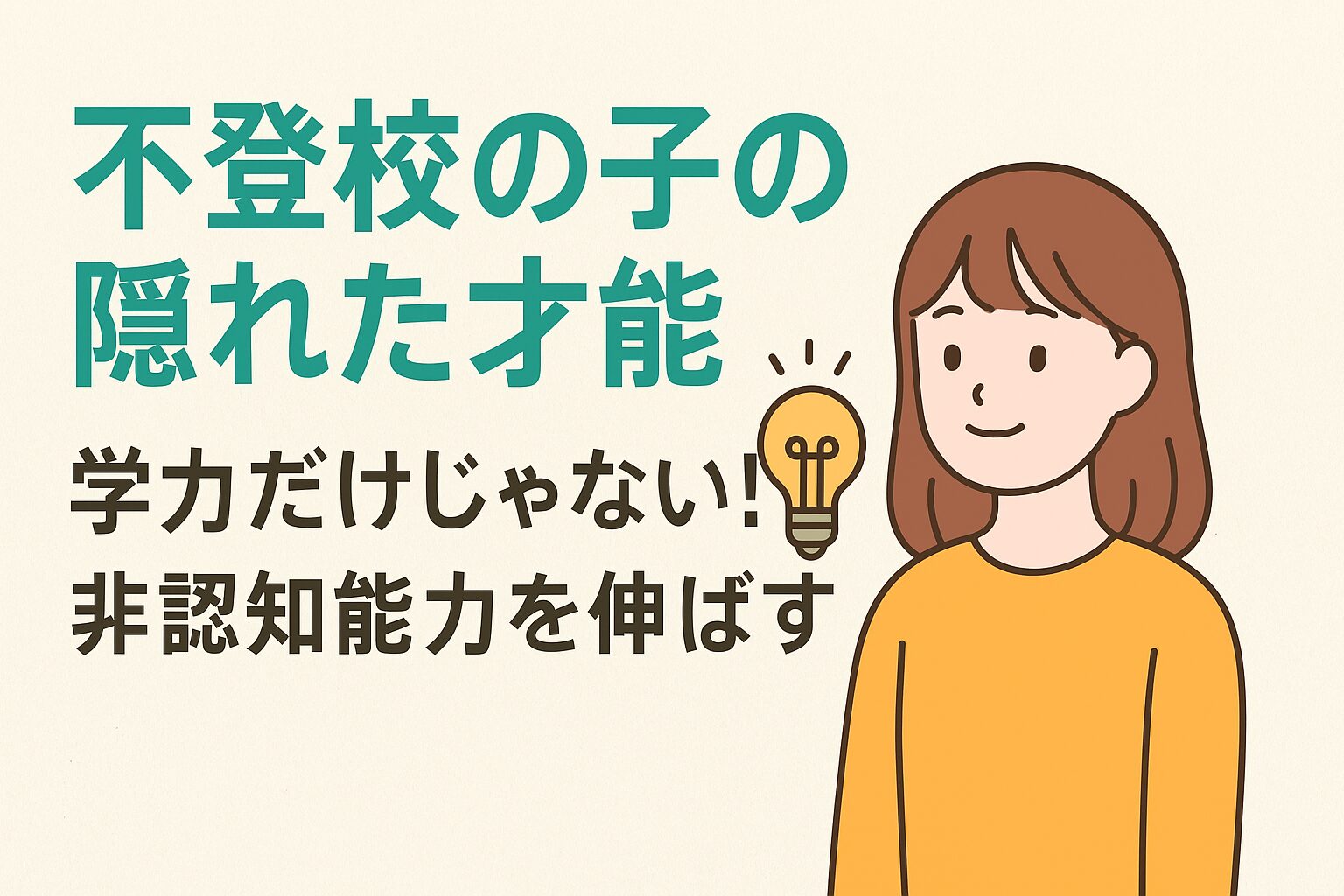
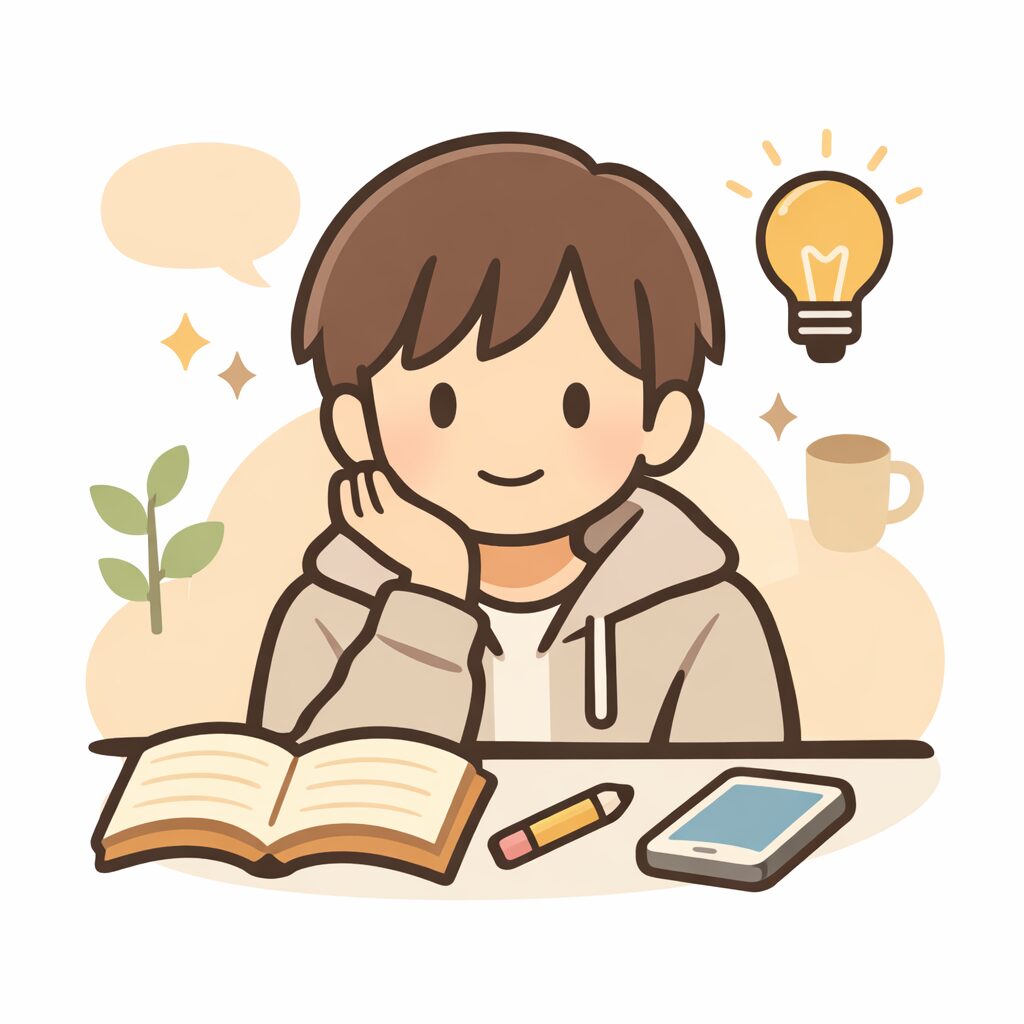


コメント