「なんでわかってくれないの?」
そう泣く子どもの姿に、胸が締めつけられたことはありませんか。
私も何度も経験しました。
うまく言葉にできない子どもを前に、つい「どうしたの?」「そんなことで泣かないの」と言ってしまう。
でも本当は、“共感してもらえた”という体験こそが、人との関わりの出発点。
この記事では、私が不登校の娘と向き合う中で学んだ
「共感の練習」と「感情を整理する習慣」についてお伝えします。

しっかり伝えたと思った夜。 こどもから、「辛い」の本音を聞いた時のショック・・・・
子どもの心をひらく“共感”の練習
「ママは、聞いてくれない」から始まった
ある夜、寝る前にぽつりと出た言葉がありました。
「ママは、わたしの話を聞いてくれない。」
この時のショックはすごかった…。
私はずっと、“聞く”よりも“整理してあげる”ことに必死だったのです。
「相手にも理由があるでしょ」
「そんな言い方したら、誤解されるよ」
――全部、正論。でも、心には届いていなかった。
次の日から、私は少しだけ意識を変えました。
アドバイスをやめて、「そうだったんだね」と返すだけにしたのです。
最初は不自然で、沈黙が気まずくて、つい言葉を足したくなったけれど、
それでも“共感”の言葉だけを残しました。
すると、少しずつ表情がやわらいでいった。
ある日、「ママ、今日はちゃんと聞いてくれたね」と言われたとき、
胸の奥で何かがほどけるような気がしました。
その夜、寝顔を見ながら「私、何を焦ってたんだろう」と思いました。
どうにか“正しい方向”へ導かなくちゃと必死で、
いつの間にか“聞く”より“直す”ことばかり考えていたんです。
でも、子どもに必要だったのは“解決”ではなく、“理解”。
「わかってもらえた」という安心があって、初めて次の一歩を踏み出せる。
そう気づいてから、私は“聞く”時間を大切にするようになりました。
🌿今日からできる「共感の練習」5つのヒント
1️⃣ すぐにアドバイスしない
→「そう感じたんだね」とまず受け止める。
2️⃣ 感情を言葉にして返す
→「それは悲しかったね」「悔しかったんだね」
3️⃣ “どうしたらいい?”と聞かない
→「今、どうしたい?」と“気持ちの今”を聞く。
4️⃣ 否定よりも確認
→「そんなふうに思ったんだね。合ってる?」
5️⃣ 沈黙を怖がらない
→言葉が出ない時間こそ、心が動いているサイン。
「共感」は、相手を変える魔法ではありません。
でも、「あなたの気持ちはここにあっていい」と伝えること。
それだけで、人は安心して他者と関わる力を取り戻します。
エネルギーを満たすことも忘れずに
すぐにやろうと思っても、親がエネルギー満タンでないとできません。
余裕がないと、短く会話を済ませたくなるし、
なかなか要領を得ず話す子どもにイライラしてしまうこともあります。
私もフルタイムで働いていたころは、帰宅してから怒涛の家事。
「なんでこんなに疲れてるのに、まだ話を聞かなきゃいけないの」と
心の中で叫んでしまう夜もありました。
でも、カフェで15分でも一人の時間をもつと、
不思議と子どもの小さな変化にも気づけるようになる。
“余裕”って、時間の長さより「心の呼吸」なんだと感じます。
そんな私の“エネルギー補給”方法はこちら。
・カフェでゆっくり過ごす
・夕ごはんは買ってくる or デリバリー
・YouTubeやAmazonプライムで気分転換
・次女や三女を抱きしめる(嫌がられますが、オキシトシンが出て優しくなれる)
・フルーツを食べる🍊
あなたの“蓄え方”はどんな方法ですか?
子どものためにも、まずは自分の心を整えることを優先してみてくださいね。
感情に名前をつける“自己理解”のサポート
「わからない」は、心の整理ができていないだけ
ある日、学校の話をしている途中で、子どもが急に泣き出しました。
「行きたくないの?」と聞くと、「わからない」と答える。
その「わからない」に、私も戸惑いました。
けれど今なら思います。
あのときの「わからない」は、気持ちに名前がつけられなかっただけなんです。
感情って、思っているより複雑です。
「行きたくない」の中には、不安・怖さ・疲れ・寂しさ・怒り……
いろんな気持ちがぐるぐると混ざっています。
それを整理するには、まず“感じることを許す”ことから。
悲しいなら、悲しいままでいい。
怒っているなら、怒っていてもいい。
「そんなふうに思ったんだね」と受け止めるだけで、
子どもは少しずつ落ち着きを取り戻します。
🌱家庭でできる「自己理解を育てる習慣」5つのヒント
先述の「共感の練習」と被るところもあります。
1️⃣ 「今どんな気持ち?」と聞く
→答えが出なくてもOK。問いを投げるだけで心が動きます。
驚かず、否定せずに聞きましょう。
親が動揺すると、子どもは話をやめてしまいます。
2️⃣ 感情を言葉にする練習を一緒にする
→「うれしい・かなしい・くやしい・こわい」などを親も口に出す。
ときには「わからないんだ💢」と返されることも。
そんなときは無理せず、また別の日に話してみましょう。
3️⃣ 否定ではなく“共感+質問”で返す
→「そう思ったんだね。どんなところがつらかった?」
私はこの“共感+質問”だけで1年過ごしたようなもの。
アドバイスはしません。
話すのは子ども、聞くのは親。
4️⃣ 感情の波を“悪いこと”と捉えない
→感情は生きている証。静かに寄り添う。
親の持論を語らず、クドクド言わず。
ただ寄り添って聞くだけで十分です。
5️⃣ 感情を記録する(書く・描く)
→見える化することで、気づきが生まれやすくなります。
スマホのメモやノートに記録しておくと、
あとで振り返ったときに「成長の軌跡」が見えてきます。
ある日、気持ちカードの中から「疲れた」を選んだ次女。
「なんで?」と聞くと、「楽しかったけど、人が多くてしんどかった」と言いました。
以前なら「そんなことで?」と思ったかもしれません。
でも今は、「そう感じたこと自体が、すごい一歩」だと思えるようになりました。

自分の心を見つめて言葉にする力こそ、“生きていく力”。
感情に名前をつけることは、心の地図を描くようなもの。
今どこにいるのかがわかると、次にどう進めばいいかが見えてきます。
感情を整理できるようになると、
子どもは「自分を理解してくれる他人」を受け入れやすくなります。
そしてそれは、自己肯定感の根っこになります。
まとめ
「共感」は、相手を変える魔法ではなく、
「あなたの気持ちはここにあっていい」と伝えること。
そして「自己理解」は、自分の中の地図を描くこと。
感情にやさしく名前をつけられる家庭が、
お子さんの“自分らしさ”を守っていきますように。
🌿あなたのお子さんは、最後に「わかってもらえた」と感じたのはいつですか?
もし思い出せないなら、今夜は少しだけ、
“答えを出さない会話”をしてみてください。
ただうなずくだけでも、心の距離は変わります。
色々と提案していますが、現状、我が家は、登校できる日が続くまで、2年かかっています。
これで順調とは思えない・・
なぜなら、進学が控えているから。中学や高校への進学となると、友人関係や環境の変化により「不登校」という状態が再燃する可能性は十分にあります。
子供自身の考え方が変わっているとか、成長するとかしていれば、環境が変わってもなんとか生きていけます。
大人でも同じ。
この変化が激しい世の中で、うまく生き抜いていく術を身につけたいと思っています。
- 【不登校】担任が何もしない?先生の対応と学校の現実
- 【不登校と習い事】やっぱりお金が必要です
- 【不登校×ペット】共働き家庭でも無理なく続いたレオパとの暮らし
- 【不登校✖️服】月曜日に揺れる朝と、気持ちを整える一着
- 【町内会がしんどい】今は「つなぐ」だけでいいと思った話

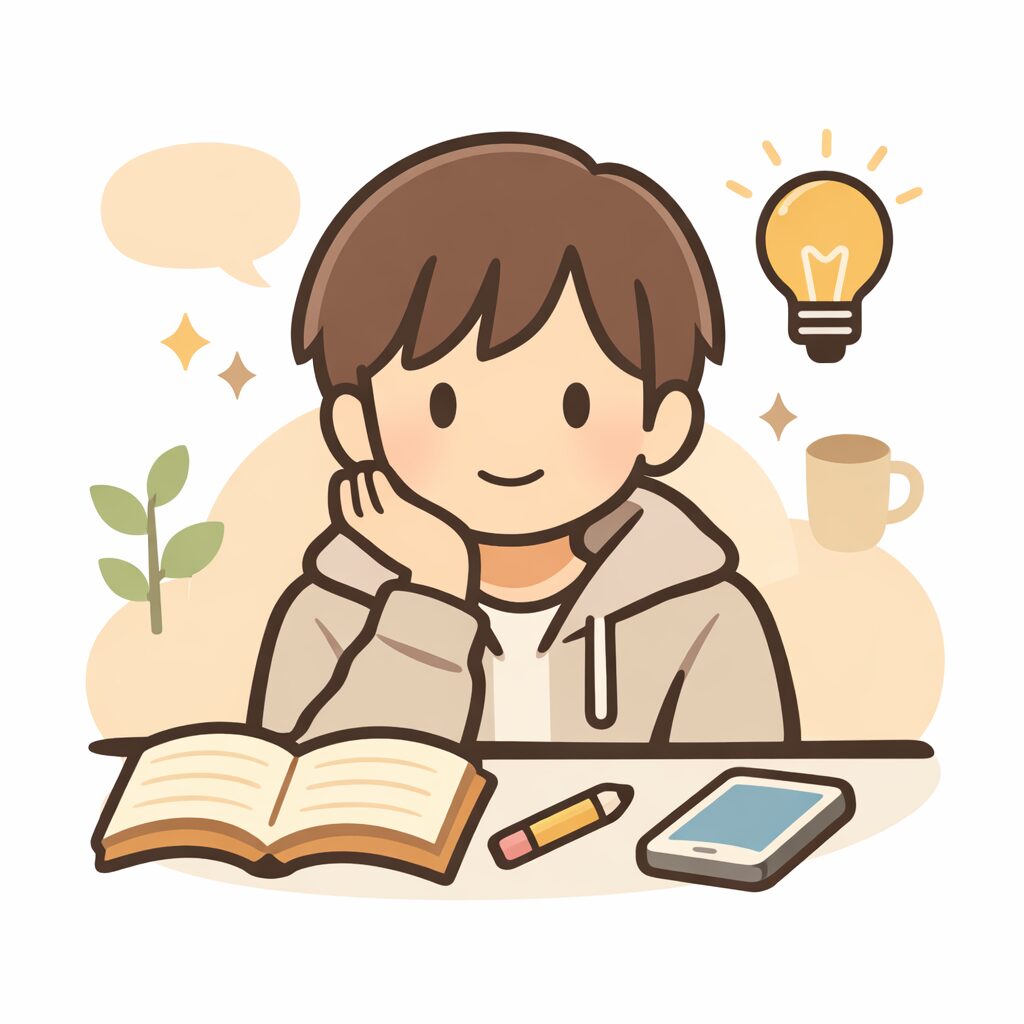


コメント