「不登校だと大学には行けないのでは?」と不安に思う保護者は少なくありません。
実際には、高校卒業資格や高卒認定を通じて、大学進学へのルートはしっかり用意されています。
ここでは、不登校経験があっても大学を目指せる進学ルートを整理します。
高卒資格があれば大学進学は可能
- 大学受験の条件は「高校卒業」または「高卒認定」
- 全日制・定時制・通信制のどの高校を出ても、卒業資格は同じ
- 高卒認定試験でも大学進学資格を得られる


私たちの時代とは、大学入試制度が違っていたり、選択肢が増えていたり・・・。
どう選んでいいかわからない・・・
入試方式の広がり
- 一般入試:学力試験で合否を判定
- 推薦入試:学校推薦型、指定校推薦など
- 総合型選抜(旧AO入試):面接・小論文・活動実績で評価
👉 学力一本だけでなく、人物や意欲が評価されるルートが増えている
不登校経験者でも使いやすいルート
- 通信制高校 → AO入試や推薦で大学進学した事例多数
- 高卒認定 → 予備校や通信教材を活用して進学
- 内申や出席日数に左右されにくい「総合型選抜」は相性が良い
大学進学の意味
- 高卒と大卒では、職種や生涯賃金に大きな差がある
- 進学することで将来の選択肢が広がる
- 「学歴」だけでなく、自己肯定感や専門的な学びを得る機会になる

不登校経験があっても、大学進学の道は閉ざされていません。
通信制や高卒認定を経由して大学へ進む生徒も多く、AO入試や推薦入試など評価方法の多様化が後押ししています。
「どんなルートを通るか」を知っておくことが、保護者の安心につながり、子どもの未来の可能性を広げます。

お金もかなり必要ですよね。
大学も公立に進学してくれたらいいけど、私立の方が選択肢が多いようなイメージです。
確かに、私立の方が、受験方法も多く、入口が広いですね。
教育費の問題は、深刻です。インフレの影響は特に学費を見ると顕著です。
奨学金をいう選択肢もありますが、卒業時に400万以上の借金を背負っての社会人スタートは誰でも辛いですよね。一つの対策案を記事にしています。
▼まず整理:AO(総合型)と学校推薦型の違い
- 総合型選抜(旧AO)
志望理由書・活動報告書などの書類に、面接や小論文、プレゼン、口頭試問、資格・検定成績などを組み合わせ、人物・意欲を多面的に評価する方式。各大学は共通テストまたは何らかの評価(小論文やプレゼン等)の活用を必須としている。文部科学省 - 学校推薦型選抜
高校長の推薦にもとづき、調査書(評定)+面接や小論文等を組み合わせて評価。こちらも共通テストまたは他の評価のいずれかを必ず使うルール。文部科学省

総合型は“大学の求める学生像(アドミッション・ポリシー)に合うか”を、書類+面接等で立体的に見る入試だよ。
年間スケジュール(高3の目安)
- 総合型:出願受付は概ね9/1以降、合否は11/1以降に発表。
- 学校推薦型:出願受付は11/1以降、合否は12/1以降に発表。
(正確な期日運用は大学ごとの要項で確認してね)
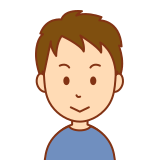
総合型や学校推薦型だと、年内に終わるんだね。
それがいいなと思うけど、難しいよね。
募集人員の上限
- 学校推薦型は、学部等ごとに定員の5割を超えない。
- 総合型(公募)は募集人員の上限規定なし(大学が独自に設定)。文部科学省
不登校経験がある場合のポイント
- 調査書の出欠状況を用いる際の留意事項の明確化や、合理的配慮の記載整備が要項・Q&Aに追記されているよ。大学は多様な背景に配慮しつつ、公正に評価する立場が示されている。
- 入学後の支援・配慮の事例はJASSOが多数公開。困りごとに応じたサポート設計の参考になるよ(面接・試験での配慮相談や在学中支援のイメージづけに)。
言い換えのコツ(面接・書類)
- 欠席の“数”ではなく、回復プロセスと学びの再開を具体的に。
- 家庭外も含む学習実績・活動(オンライン講座、資格、制作物、ボランティア等)で“学び続けた証拠”を示す。
- 志望分野と結びついた探究やアウトプット(作品・ミニ研究・発表動画)を添える。
出願までに用意する書類(チェックリスト)
- 志望理由書/学修計画書(大学指定様式)
- 活動報告書(文科省がイメージ例を公開)
- 調査書(高校発行)・推薦書(学校推薦型のみ)(文科省のイメージ例あり)
- 資格・検定の合格証やスコア、実績資料(大会・発表・作品 等)
- ポートフォリオ(芸術・情報系など)
文科省ページには活動報告書・推薦書のイメージ例が掲載されているよ。文部科学省
対策:これだけ押さよう!
小論文
- 志望領域の基礎知識+社会的背景→自分の問い→根拠と具体例→結論の順で。
面接 - 「志望理由」「入学後の計画」「将来像」「高校時代の学び直し」への一貫性。
プレゼン・口頭試問 - スライドは問題→仮説→方法→結果/学び→今後の5点を簡潔に。問いへの再現性と学びの次アクションを明確に。
総合型は“書類+面接等+(必要に応じ学力・実技)”で評価されるのが基本。大学によりGDや模擬講義レポートなどの課題もあるよ。
▼高2〜高3の行動タイムライン
- 高2 春〜夏:志望領域の読書・MOOC・資格、探究のテーマ設定
- 高2 秋〜高3 春:探究の成果物(レポート/作品/発表動画)を作る
- 高3 6〜8月:志望校のアドミッション・ポリシー精読、書類ドラフト・面接練習
- 高3 9〜12月:総合型・推薦の出願/本番(一般併願の準備も並行)KEIHER Online.
そのまま使える“ひな形”
志望理由書(3段落)
- 志望動機:関心領域+きっかけ(体験・探究テーマ)
- 学修計画:入学後に取り組む科目・研究・課外活動(具体名)
- 将来像:学びの社会実装・貢献のイメージ(卒業後の道)
活動報告(箇条書き)
- 期間/役割/目的/成果(数値・受賞・発信先)/学んだこと/次のアクション
面接の想定Q
- なぜこの学部か?高校時代の学び直しで得たことは?最近感銘を受けた論点は?入学後1年目の計画は?
▼まとめ
AO・推薦は、“今の力とこれからの伸び”を見てもらえる入試。
出欠の数字だけで判断されるわけじゃないよ。公式の枠組みも“多面的評価”と“配慮”を整えて進んでるから、探究の証拠と計画性をコツコツ集めていきましょう。

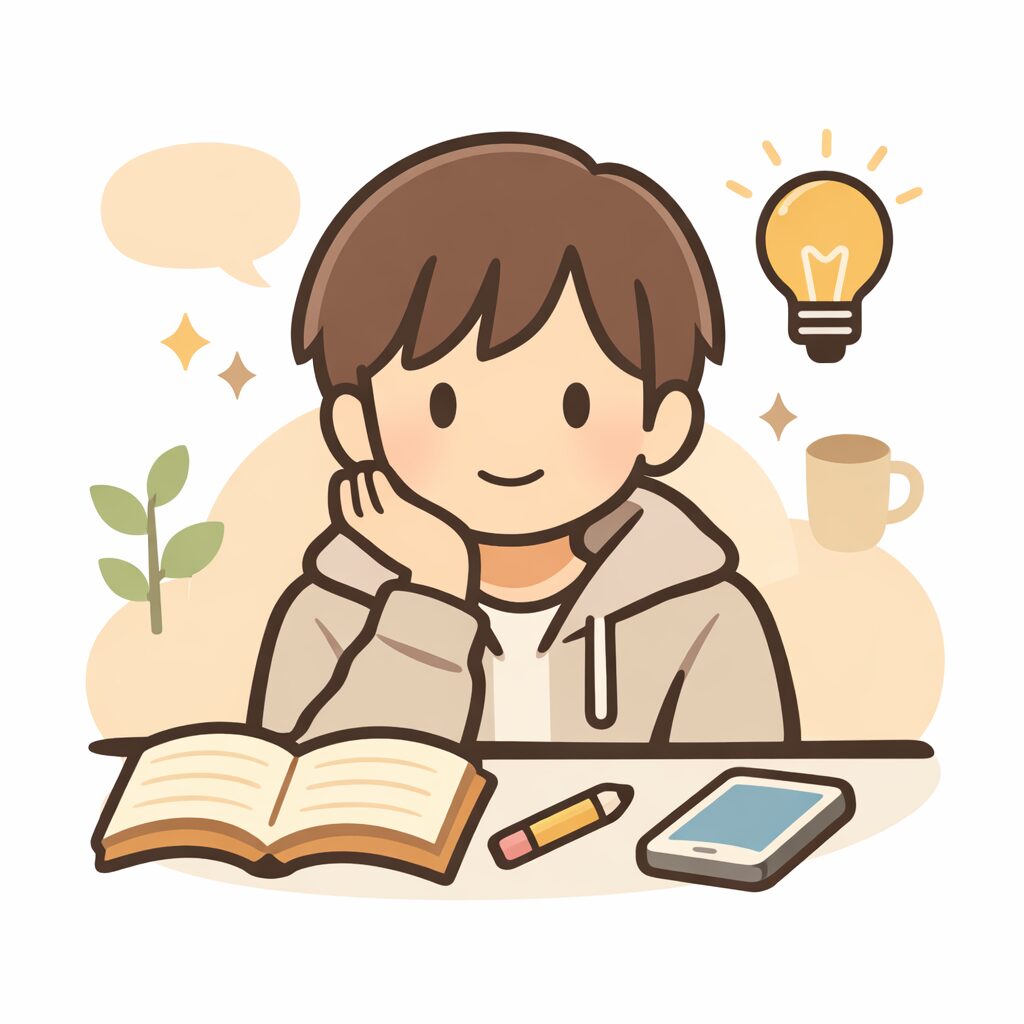


コメント