私の育て方が悪かったのかもしれない
子どもが学校に行けなくなったとき、多くの親が最初に抱くのはこの思いです。朝起きられない子どもを前に、「どうしてうちの子だけ?」と涙したり、SNSや周囲の声に「親のせい」という言葉を見つけては、まるで胸を刺されるように苦しくなる。
でも、あなたは一人ではありません。
不登校は今や特別な出来事ではなく、全国で34万人以上の小中学生が経験しています。そして、その子どもを支える親たちが、あなたと同じように孤独や罪悪感と向き合っています。
この記事では、不登校の親が感じる辛さの正体を解き明かし、不登校を「問題」ではなく「サイン」として捉え直す視点、家庭でできる関わり方、家事を通じた自己肯定感の育み方、そして社会的なサポートの活用まで、5つのステップで整理してお伝えします。
「子どもを無理に変えようとしなくても大丈夫。親子の関係を整えながら、一歩ずつ歩んでいけばいい」
そう思えるように、少しずつ心を軽くしていきましょう。
第1章:あなただけじゃない。不登校の親が抱える「辛さ」の正体
お子さんが学校に行けなくなった朝。布団から起きられず涙ぐむ姿を見て、「どうしてうちの子は…」と胸が締め付けられる。そんな経験をしたことはありませんか?
多くの親は、最初に「私のせいだ」という自責感にとらわれます。
ある調査では、不登校の子を持つ親の66.7%が「原因は自分にある」と感じ、53.1%が「孤独感」を抱いていました。
不登校は2023年度で全国に34.6万人。40人学級なら1〜2人の子が不登校という割合です。
決して珍しいことではありません。けれども、不登校の子はまだ「少数派」。世間からの偏見や厳しい視線を受けやすく、親は孤立しやすいのです。
親が感じる三つの「辛さ」
- 罪悪感:「私が甘やかしたから」「しつけが悪かったから」
- 孤独感:「誰にも相談できない」「話しても理解されない」
- 焦り:「学習が遅れてしまう」「将来どうなるの?」
ある母親はこう話しています。
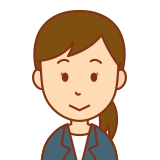
「無理にでも連れて行った方がいいのかと何度も思いました。
でも実際に無理やり登校させた日は、子どもが玄関で泣き崩れ、さらに心を閉ざしてしまったんです」
あなたが感じている辛さは、決して「弱さ」ではなく、同じ状況にある多くの親が抱える共通の感情です。
第2章:不登校は「問題」ではなく「サイン」。子どもと家庭に起きていること
「学校に行けない=怠け」と考えてしまう人は少なくありません。
ですが、不登校は決して単純なものではなく、さまざまな背景が絡み合った結果として現れる「サイン」です。
不登校の背景にあるもの
- 身体的要因:起立性調節障害など、自律神経の乱れによって朝起きられず、体調がすぐれない。
- 発達の特性:集団行動が苦手、音や光に敏感、友達との関係づくりに困難さを抱える。
- 家庭環境:母親の体調不良や介護によって子どもが家事を担い、ヤングケアラー状態になる。
- 学校での経験:勉強が難しい、部活動のプレッシャー、人間関係のトラブルやいじめ。
ある専門家はこう指摘します。
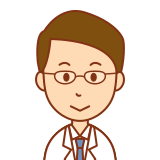
「不登校は“問題のある子”ではなく、“問題に直面している子”。その子なりのSOSであり、生きるための工夫でもあるのです」
海外に目を向けると、フィンランドでは「学校に合わない子がいるのは自然なこと」と考え、子どもが安心できる別の学びの場を柔軟に提供します。
日本でも「不登校=才能の芽生え」として、新しい進路を切り開く子どもたちも増えています。
第3章:家庭でできること① 「無理強い」をやめて始める信頼関係の再構築
「学校に行きなさい!」と叱ることが、かえって子どもとの距離を広げてしまうケースは少なくありません。焦る気持ちは自然ですが、今大切なのは「信頼関係の再構築」です。
信頼を育てる関わり方
- 話を最後まで聞く:「そう思っているんだね」と共感で受け止める。
- 存在を尊重する:「学校に行くかどうか」ではなく、「あなたがいてくれるだけで大切」と伝える。
- 家庭を安心できる場所にする:親同士が協力し、夫婦の不安を子どもにぶつけない。
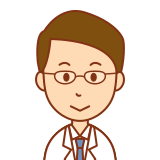
家族療法の観点では、不登校は家族全体のバランスの乱れを映す鏡とも言われます。親が落ち着きを取り戻すと、子どもも少しずつ安心を取り戻すのです。
段階ごとの関わり方
- 初期(エネルギーが枯渇している時期):まず休養を優先。
- 停滞期(少し動けるようになった時期):小さな役割を任せる。
- 回復期(外の世界へ関心が戻る時期):フリースクールや地域活動につなげる。
焦りを手放し、子どものペースを尊重することが何よりの近道です。
第4章:家庭でできること② 「家事」で育む、子どもの自己肯定感と才能の芽
「学校に行かないのに家事をさせるなんて…」と思うかもしれません。ですが、実は家事は子どもにとって自己肯定感を育む大切な機会です。
家事がもたらす3つの効果
- 役割を持てる:「自分は家族に必要とされている」と実感できる。
- 感謝される体験:「ありがとう」が自信になる。
- 生活リズムが整う:毎日のルーティンが自然にできる。
ある家庭では、料理を任された子が「自分でレシピを考えたい」と言い出し、そこから料理の世界に興味を広げました。家事は「才能の芽」を発見するきっかけにもなるのです。
【今日からできる家事の例】
- 食器洗い
- 洗濯物を干す・たたむ
- 簡単な料理や盛り付け
- 掃除やペットの世話
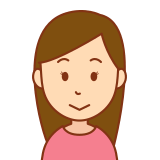
小さな「ありがとう」の積み重ねが、子どもの心を支える大きな力になっていくんですね。
第5章:一人で抱え込まない。親子を支える社会のサポートを活用しよう
不登校は親にとっても大きな挑戦です。経済的な負担、精神的な孤立感…その両方を抱えてしまう人は少なくありません。
ある調査では、不登校をきっかけに家計が増加した家庭は約9割。
フリースクールの費用、通院費、食費の増加が主な要因です。また、親の3割が働き方を変えざるを得なかったとも報告されています。
活用できる社会資源
- スクールカウンセラー(SC):不登校相談の多くを占め、保護者支援も行う。
- 親の会・コミュニティ:同じ経験を持つ親とのつながりで孤独感が和らぐ。
- フリースクール・教育支援センター:学校外で安心して学び、人と関われる場所。 「不登校が通えるフリースクール】についての記事はこちら👆
- 自治体の補助制度:利用料補助や支援金制度が広がっている。
- 家事代行や福祉サービス:家庭全体の負担を減らす。
「親が笑顔でいられること」が、子どもにとって一番の安心です。
どうか一人で背負わず、社会の手を借りてください。
まとめ
今回は「不登校に悩む親の心を軽くする5つのステップ」を紹介しました。
- 孤独や罪悪感はあなただけではない
- 不登校は「サイン」として捉える
- 信頼関係を再構築する
- 家事で自己肯定感と才能の芽を育む
- 社会的サポートを積極的に活用する
子どもの不登校は、決して親のせいではありません。
あなたが一歩立ち止まり、子どもの気持ちに寄り添いながら歩んでいくこと自体が、子どもにとっての力になります。
どうか「一人で抱え込まないで大丈夫」と心に刻んでください。
小さな実践の積み重ねが、やがて大きな安心と未来への希望につながります。
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます。
不登校は、親にとっても子どもにとっても長い道のりのように感じるかもしれません。けれども、その一歩一歩が、確かに親子の絆を深め、未来へとつながっています。
どうか「あなたはひとりじゃない」ということを忘れないでくださいね。
そして、今日からできる小さな一歩をぜひ試してみてください。
あなたとお子さんの毎日が、少しでも穏やかで、温かな光に包まれますように。
◇関連記事のご案内
- 【教育費をどう準備する?】不登校でも安心できる家計の考え方
- 【宅食×不登校】子どもと親がラクになる!我が家の宅配ごはん活用術
- 【フリースクールってどう?】費用・選び方・体験談まとめ
- 【教育無償化とは】制度を知って家計の負担を軽くしよう

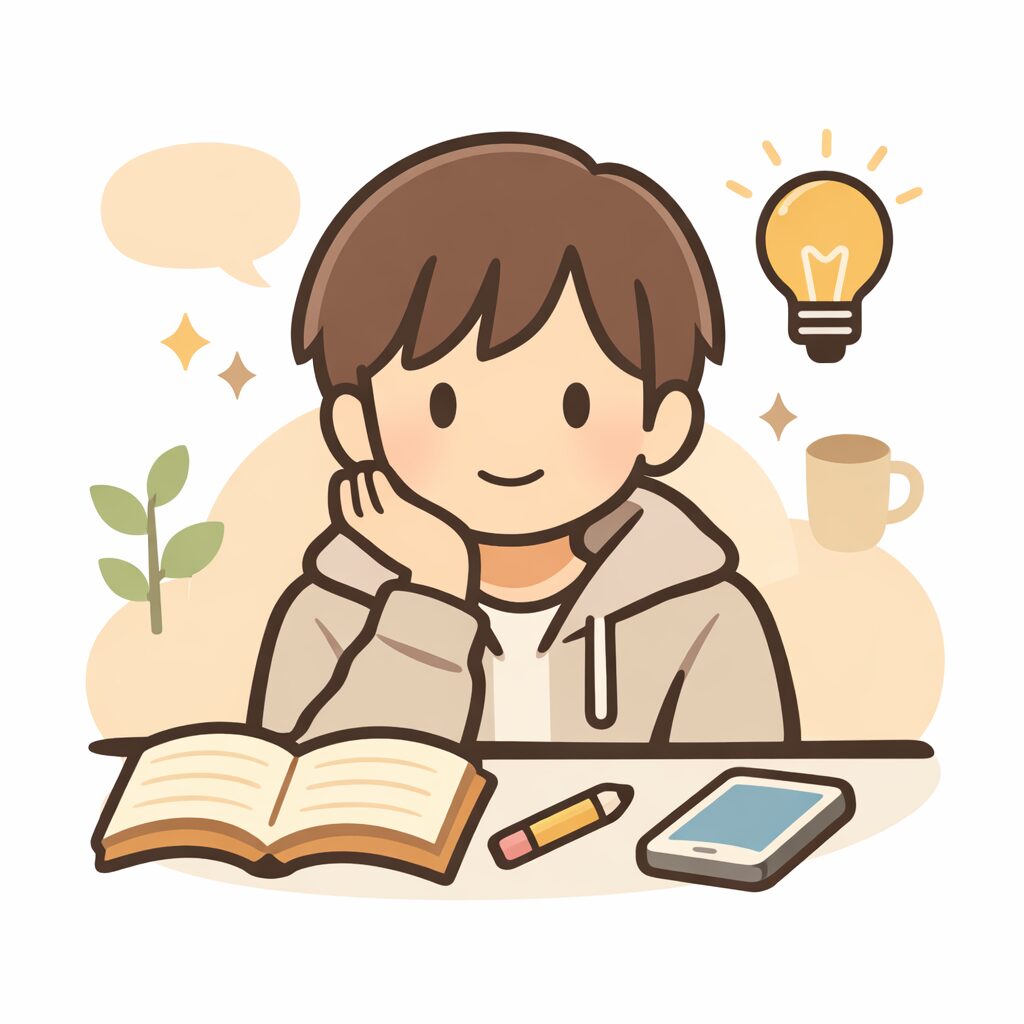
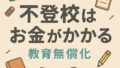

コメント