学校にどう伝える?親の迷い
子どもが休みがちになると、毎朝の学校への連絡がちょっとしたプレッシャーに感じられますよね。
「先生に正直に話したほうがいいのかな…」
「全部説明したら、かえって迷惑かな…」
そんなふうに、どこまで伝えるかで迷う親御さんはとても多いです。
毎朝の連絡はシンプルでOK
学校への連絡は「今日は休みます。体調は落ち着いています」など、短くて十分。
理由を細かく説明しようとすると、親自身も疲れてしまいますし、先生にとっても毎日の長文は負担になります。
「無理に理由を書かなくてもいい」と思えると、親の気持ちもぐっと楽になります。
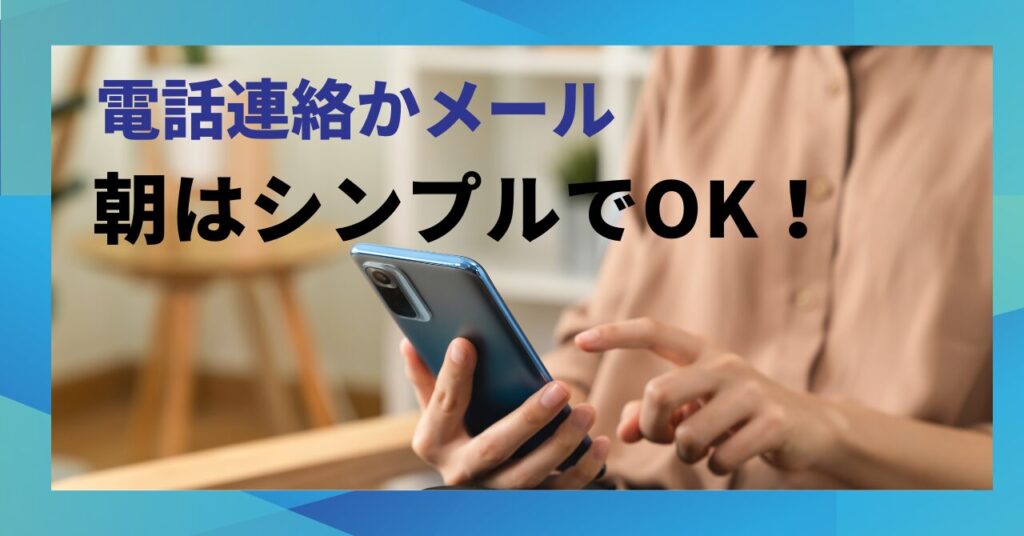
不登校児を担任する先生の大変さ
不登校の子どもを担任している先生も、実はとても悩みながら動いています。
- クラス全体を見つつ、不登校の子にどう関わるか
- 無理に登校を促して逆効果にならないか
- 家庭への関わり方や頻度はどうすればよいか
担任によって対応の仕方はさまざまですが、共通しているのは「正解が分からない中で手探りをしている」ということ。
だからこそ、保護者から「家庭では落ち着いて過ごしています」と一言添えるだけでも、先生は安心できるのです。
文科省が示す学校の支援体制(担任だけで抱え込まないことの大切さ)
文部科学省は「不登校児童生徒への支援は、担任1人に任せず、多くの教職員や関係機関で連携して対応すること」が重要だと明示しています。
具体的には、担任以外にもスクールカウンセラーや教育相談担当、養護教諭、管理職などが関わり、チームで支援計画を立てる仕組みが求められているんです。
現場のリアルな声:「担任だけに負担が集中してしまう」
ところが実際には、担任教諭が中心となって対応するケースが多く、長時間労働の中で「もっと時間さえあれば…」と悩む先生も少なくありません。
また、管理職や支援体制がある学校ばかりではなく、担任にだけ頼られて現場が孤立してしまっていることもあります。
現場の先生だけでは限界があります
こうした背景を踏まえると、「学校にだけ支えてほしい」と期待するのは難しく、担任に負担が集中してしまう現実も理解しておくことが大切です。
だからこそ、親としては「学校以外の支援につなげてほしい」「お任せになりすぎないよう協力します」と伝えることが、先生や学校にとっても協働しやすくなる要素になります。
他の不登校児の様子を聞いてみる
もし余裕があれば、「他のお子さんはどんな対応をしているんですか?」と先生に尋ねてみるのも良い方法です。
- 「カウンセリングだけ受けている子はいますか?」
- 「保健室登校をしている子はいますか?」
- 「もしそうなら、うちの子の登校曜日を重ならないようにしたいのですが…」
こんなふうに聞くと、学校側も「家庭が前向きに考えてくれている」と感じてくれます。
相談は箇条書きにして伝えるとスムーズ
学校にお願いしたいことや相談は、箇条書きにしてメールで送るのがおすすめです。
- 授業のプリントをもらえるか
- 登校するならどの曜日がいいか
- 保健室利用のルールを知りたい
文章で整理しておくと、先生も確認しやすく、誤解も生まれにくくなります。
一度学校訪問して話すと、信頼が深まる!
とはいえ、メールだけでは顔が見えない分、何かと心配です。
可能であれば、放課後などに短い時間をいただいて、先生と直接顔を合わせて話すのも効果的です。
「家庭ではこんな様子です」と伝えておくと、先生も「この保護者は協力的だな」と安心してくれます。
一度話しておくだけで、後々のやりとりがスムーズになり、学校側も親を「前向きなパートナー」と見てくれるのです。

現場の声と気をつけたいこと
もちろん、現場にはさまざまな立場の声があります。
- 先生の立場:「毎日の連絡が負担になる」という声もあります。だからこそ、担任だけに任せず、スクールカウンセラーや外部の支援につなぐのも大切です。(→次章で詳しく)
- 他の保護者の立場:「他の子のことを聞くのはプライバシー的に不安」という人もいます。なので“全体的な傾向を知りたい”という聞き方が安心です。
- 担任の年齢や経験による違い
- 年配の先生 → 「甘やかしすぎ」「学校に来れば楽しくしてますよ」と言いがち
- 若い先生(経験浅め) → 「何かしてあげたいけど方法が分からない」と悩みがち
- 若い先生(別タイプ) → 「不登校児は負担」と感じてしまう人も
だからこそ、周りのママ友や地域のつながりから「どんな先生なのか」を知っておくことはとても役立ちます。伝え方を工夫する材料になりますし、学校に協力的な姿勢を見せられます。

- 担任への連絡はシンプルに+家庭での様子を一言添える
- 学校訪問や放課後面談を一度お願いする
- 周囲の保護者から先生の人柄・スタンスを知っておく
- 学校以外の支援先を視野に入れる
こうした工夫をすることで、保護者側も「孤独に戦っている」気持ちから解放されやすくなり、先生も「この家庭なら協力し合える」と前向きに感じてくれます。
まとめ
学校とのやり取りで大切なのは、
- 連絡は短く・正直にすること
- 先生も迷いながら支えていると知ること
- 他の不登校児の取り組みを聞いてみること
- 相談は箇条書きにしてメールで送ること
- 一度学校訪問をして顔を合わせておくこと
- 学校以外の支援を視野に入れること
文科省は「担任が一人で抱え込まない体制づくり」を求めていますが、現場では担任に負担が集中してしまうこともあります。

そのため、保護者側から「協力します」という姿勢を示し、学校だけでなく外部支援も視野に入れておくことが、親も先生も一緒に歩んでいく支えとなります。
不登校は親だけでも先生だけでも抱えきれません。お互いが協力しやすい関係を築くことが、子どもにとって大きな支えになります。
次の記事では、フリースクールや支援制度など“不登校でも使える選択肢”についてまとめていきますね。

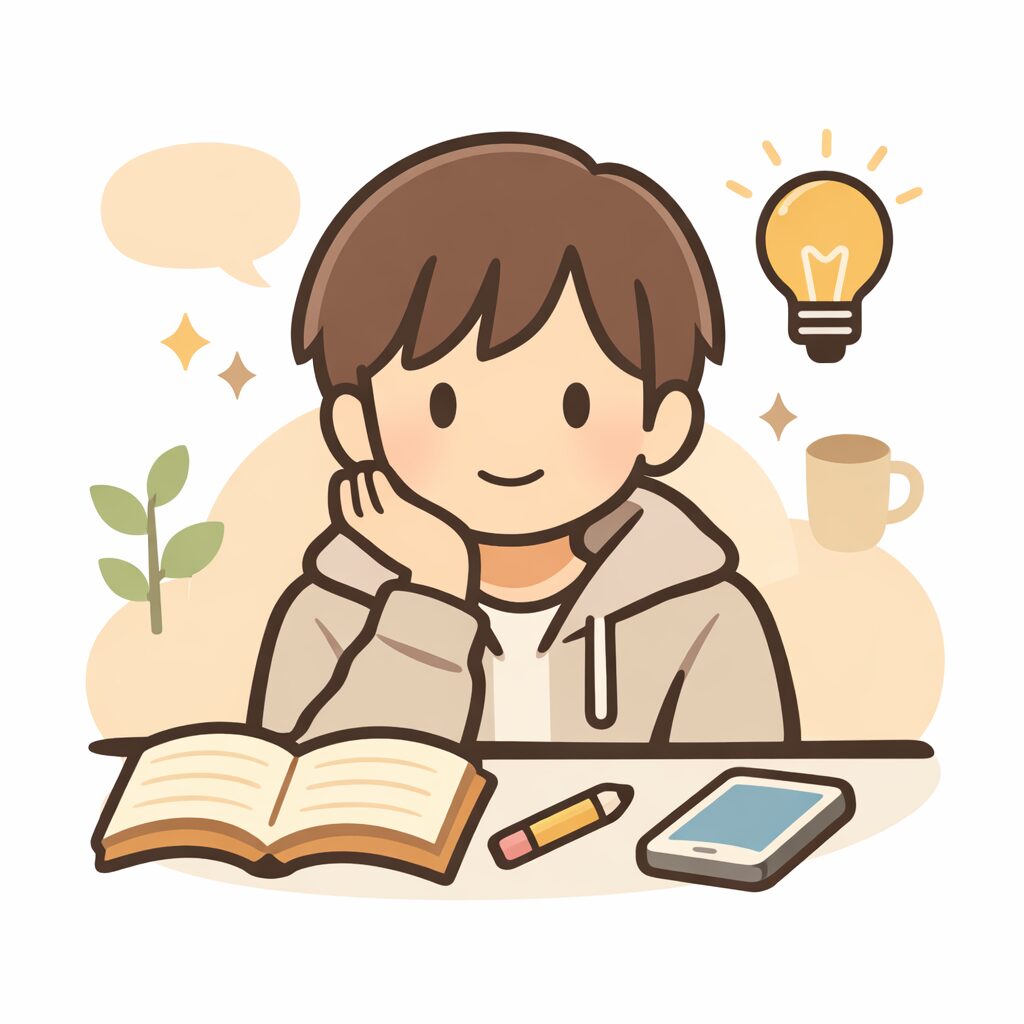


コメント