学校に行けない日が続くと、「家以外に安心して過ごせる場所はあるのかな」と不安になりますよね。
でも関西には、フリースクールや教育支援センターなど、安心できる環境があります。さらに、実際に体験した親子の声をまとめたので、あなたの気持ちにも寄り添える内容になっています。
👉 全国データ
全国で実際にフリースクールに通っている小中学生は約1万人ほどと推計されています(文科省調査)。
不登校の子どもは34万人を超えているので、通っているのは全体の約3%、およそ30人に1人の割合です。
数字だけを見ると少数派ですが、「居場所がある」と知ることが大きな安心につながります。
▼関西のフリースクール(民間)
| 施設名 | 場所 | 費用目安 |
|---|---|---|
| フリースクールFlower | 大阪府枚方市 | 入校金 約15,000円、 月謝 約40,000円 |
| フリースクール キリンのとびら | 大阪府泉佐野市 | 入学金 50,000円、 年間登録料 10,000円、 月謝 30,000〜40,000円 |
| フリースクールここ | 吹田市・大阪市 | 入学費 20,000円、 登録料 10,000円、 月謝 約40,000円 |
| フリースクール・ パーソナルアカデミー | 大阪府池田市 | 市内在住は無料、 市外は月24,000円〜(減免あり) |
▼関西の教育支援センター(公的機関)
| 施設名 | 場所 | 費用 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 教育支援センター | 大阪市 | 無料 | 学習支援・心理相談・出席扱いの可能性あり |
| 八尾市 教育支援センター「さわやかルーム」 | 八尾市 | 無料 | 小集団で活動、体験入室も可能 |
| 堺市 教育支援教室 | 堺市 | 無料 | 登校準備に活用できる主体的プログラム |
| 神戸市 教育支援センター「くすのき教室」 | 神戸市 | 無料 | ICT・通級・カウンセリングを併設 |
| 京都市 教育相談総合センター | 京都市 | 無料 | 専門職による相談窓口あり |
▼不登校経験者・保護者の声
- 「安心できる場所ができた」
「フリースクールに通い始めて“ただいるだけでいい”と言われたことが、子どもにとって大きな救いになりました」
出典:DLIVEブログ - 「親の会で支えられた」
「同じ立場の声を聞き、心の負担が軽くなった」
出典:通信制高校ナビ - 「費用負担が不安」
保護者の86%が「子どもの対応や将来が不安」、75%が「費用の少ない学びの場を望む」と回答。
出典:多様な学びプロジェクト - 「元不登校の子が今はスタッフに」
小学2年から中学卒業まで不登校だった女性が、今はフリースクールのスタッフとして子どもを支えている。
出典:たよりの広場
▼なぜフリースクールに通う子が少ないのか?
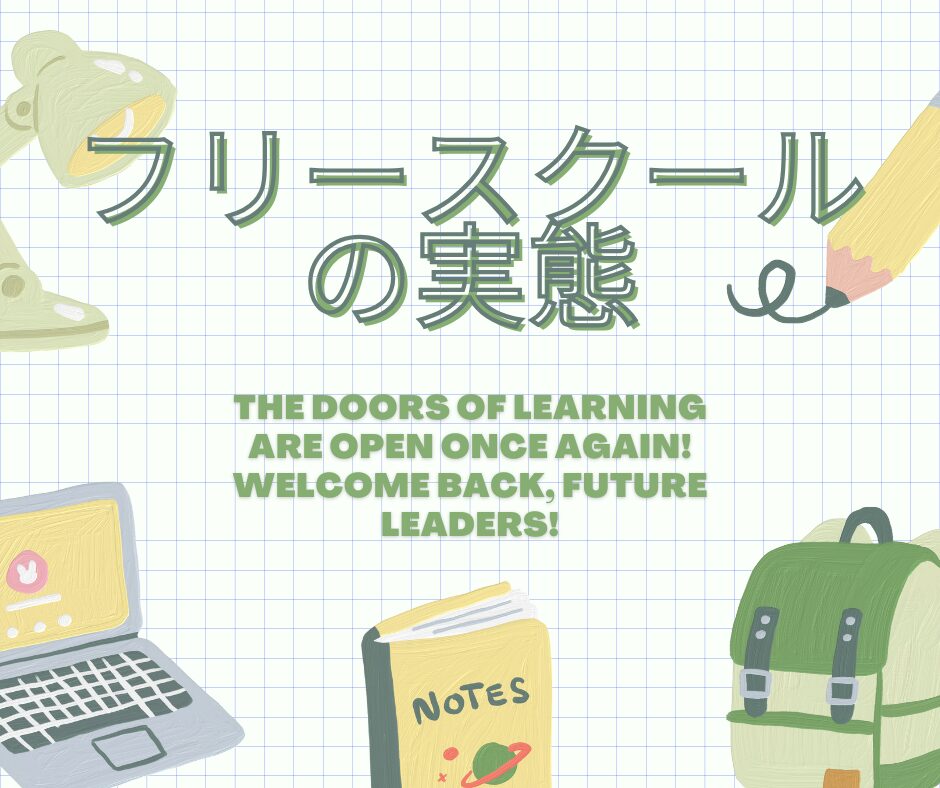
- 施設不足:全国で400〜500程度しかなく、地方では通いたくても近くにない
- 費用負担:月謝2〜5万円、入会金など経済的ハードル
- 心理的要因:「学校にも行けないのに、また別の場所に行くのはつらい」と感じる
- 学校背景:いじめ・人間関係など根本的な問題が未解決のまま
▼なぜフリースクールは高いのか?
ここで、そもそもフリースクールとは・・・という視点となぜ費用が高いのか・・・
まとめてみました。
フリースクールの平均的な費用は、
- 入会金:約5.3万円
- 授業料(月額):約3.3万円
と報告されています(文科省調査)。 - 高いところでは入会金10万円、月額5万円を超える例もあります。
理由はシンプルで、ほとんどのフリースクールが民間運営だから。
- 公的な助成が少なく、家賃・教材費・人件費をすべて自己負担
- 少人数や個別対応をしているため、人件費がかかる
といった背景から、どうしても費用が高額になりがちです。
一方で、鎌倉市など一部自治体では月謝の一部補助制度(3分の1、上限1万円)を導入している例もあります。
👉 出典:surala.jp, comotto.docomo.ne.jp
▼文科省がフリースクールをどう考えているか

文部科学省はフリースクールを「学校以外の重要な学び・居場所」と位置づけ、
以下の方針を打ち出しています。
- 不登校の解決=登校再開ではない
→ 子どもが自らの進路を主体的に考え、社会的自立ができるよう支援することが大切。 - 公的支援との連携強化
→ 学校・教育委員会・スクールカウンセラー・教育支援センターなどとの連携を推進。 - 出席扱い制度の整備
→ フリースクールなど外部施設での学習も、条件を満たせば学校の出席として認める制度あり。
(保護者と学校の連携、学習内容の妥当性確認などが必要)
👉 出典:mext.go.jp, note.com, megaphone.school-voice-pj.org
▼それでもフリースクールを選ぶメリットとは?
- 安心できる居場所ができる(ただ過ごすだけでOK)
- 少人数・個別ペースで学べる
- 進学につながる道がある(出席扱いや提携校)
- 社会とのつながりを保てる
- 親もサポートを受けられる
▼関西の具体的な事例
くらら庵(京都市/NPO法人 Reframe)
- 朝倉美保さんが代表。2021年開設。
- 「来ても帰っても自由」で安心できる居場所。
- 登録25名、1日8〜10名利用。
- 京都市内10校と連携し、利用日を出席扱いにできる仕組みあり。
👉 出典:京都新聞 福祉タイムズ
ろすい塾(京都市)
- 発達障害・不登校の子ども向け少人数制の個別指導塾。
- 1対3までの体制、学習+進路+生活サポート。
- 子どもの集中力に合わせて柔軟に指導。
👉 出典:ろすい塾公式
和草(にこぐさ/奈良県生駒市)
- 古民家を利用した自由な居場所。
- 「100%自由」を掲げ、子どもが自分で過ごし方を決められる。
- 現在16名が通い、自己肯定感を取り戻す場として注目。
👉 出典:greenz.jp
まとめ
全国的にはフリースクール利用は不登校全体の3%と少数派。
けれど関西には「くらら庵」「ろすい塾」「にこぐさ」のように、学校に行けない子どもに安心できる居場所を提供し、学びや進学につなげる取り組みが広がっています。
「学校に行けない=終わり」ではなく、「学校以外の選択肢もある」と知ることが、親と子どもの大きな支えになるはずです。
▼全体のまとめ
不登校は年々増加しており、全国では小中学生34万人以上が学校に行けない状況にあります。
そのうちフリースクールに通っている子どもは約1万人、全体の3%ほどと少数派ですが、
関西には「くらら庵」「ろすい塾」「にこぐさ」のように、安心できる居場所と学びを提供する拠点があります。
親としてできることは「学校だけに頼らない」「複数の選択肢を知っておく」こと。
フリースクールや教育支援センター、地域の居場所を知っているだけでも、心の余裕につながります。
子どもにとって大切なのは、「学校に行くこと」よりも「安心できる環境で、自分らしく過ごすこと」。
この記事が、次の一歩を考えるきっかけになれば幸いです。
▼関連記事のご案内
あわせて読みたい記事はこちら👇
👉 この記事とあわせて読むことで、データ・親の対応・学校との関わり・外部の居場所という4つの視点から、不登校を包括的に理解できます。
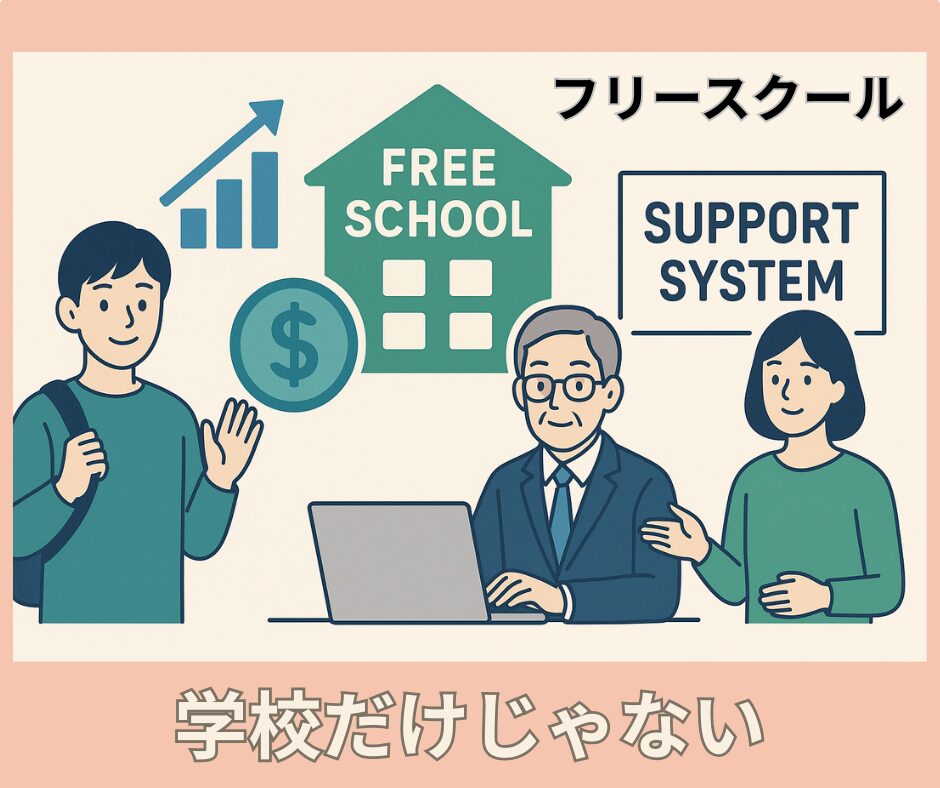
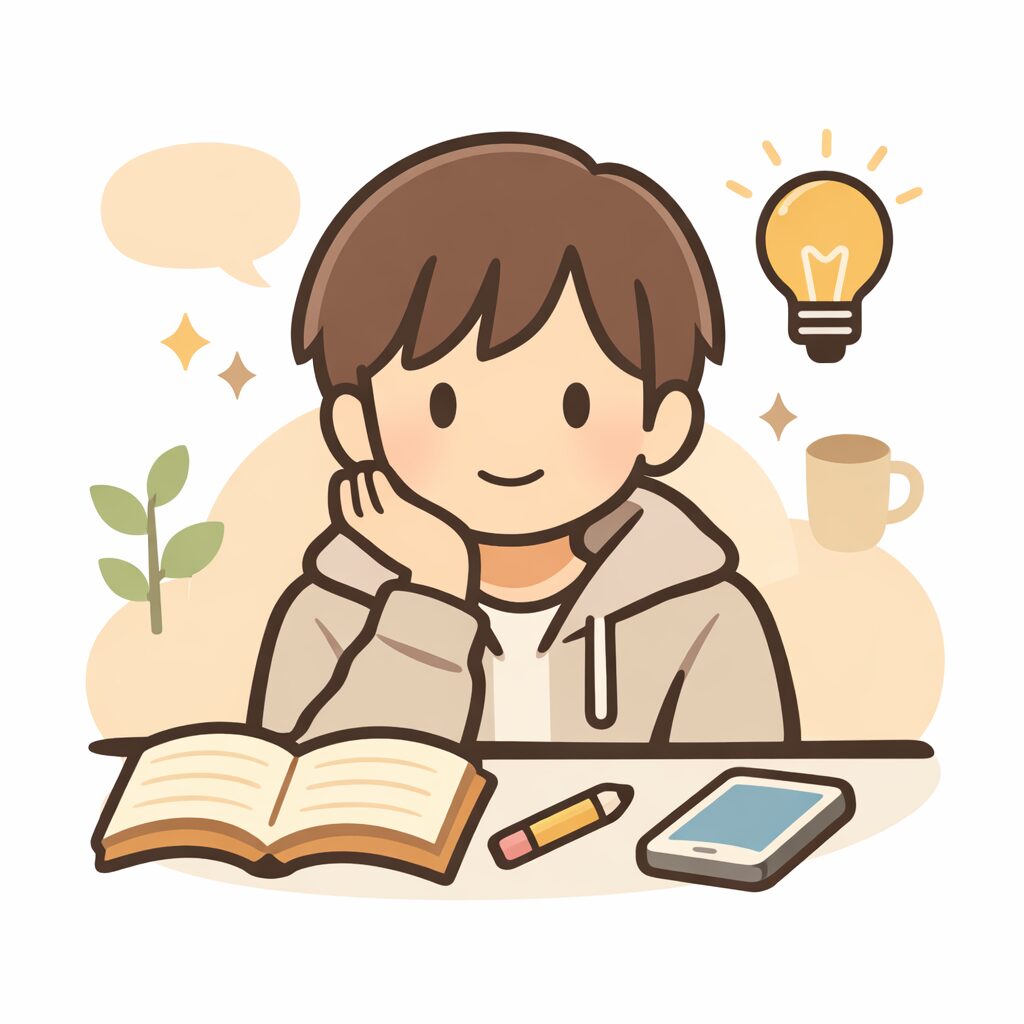


コメント