▼はじめに
「学資保険に入っておけば安心」と思っていませんか?
実は教育費はインフレの影響を大きく受けており、貯金や保険だけでは追いつけない可能性があります。この記事では、具体的な数字とシミュレーションを交えながら、教育資金を「貯金+投資」で備える方法を解説します。

▼教育資金はなぜインフレに弱いのか
インフレってどういうこと?
「インフレ」とは、物の値段がじわじわ上がっていくこと。
たとえばスーパーでよく買う玉ねぎや牛乳を思い出してみてください。
- 去年は1袋198円だった玉ねぎが、今年は298円になっている
- 牛乳も気づけば1本200円台後半になっている😨。
こんなふうに、同じ商品なのに値段が少しずつ上がっていくのがインフレです。
つまり「同じお金で買えるものが減ってしまう」現象なんです。
教育費は物価以上に上がりやすい分野です。
- 1970年〜2015年の45年間で物価は約3倍
- 同期間で教育費は約7倍に上昇
- 国立大学学費:1989年→2016年で1.56倍
- 私立大学学費:同期間で1.37倍
現在、大学進学に必要な金額は約450万円ですが、年率0.5%のインフレを18年間考慮すると
約492万円 !
つまり、ただ貯金しているだけでは 42万円不足 する計算になります。

▼学資保険のデメリット
インフレだから、お金を貯金しても・・・じゃ【学資保険】!!
ちょっと待ってくださいね!
学資保険は「安全そう」に見えますが、弱点も多いです。
- インフレに負ける低利回り
平均年利0.3%程度。インフレ率0.5%なら実質的にマイナス。 - 元本保証ではない
保険会社が倒産した場合、預金保険制度のような保護はありません。 - 元本割れのリスク
途中解約で元本割れ。満期でも総支払額を下回る商品があります。よく調べてみましょう。昔(10年前でもすでにそのような商品に出会いました・・・💦) - 資金拘束が強い
長期にわたってお金が固定され、急な出費に対応できません。

学資保険に入る方は、おそらくお子さんがお生まれになってから、すぐ購入される方が多いかと思います。でも7歳ぐらいまでは入れますよーっていう宣伝も受けたことあります。
▼学資保険は0歳から、遅くても7歳くらいまで入れる
学資保険は「子どもが生まれたらすぐに入る」というイメージがありますが、実際には小学校入学前(6〜7歳)まで加入できる商品が多いです。中には「12歳までOK」という保険会社もあります。
一見「まだ入れるんだ」と思うかもしれませんが…実はそこに落とし穴があります。
遅く入るとどうなる?
- 毎月の保険料が高くなる
- 返戻率(受け取れるお金の割合)が下がる
- 元本割れのリスクも高まる
- そもそも選べる商品が少ない
つまり「後からでも入れる=安心」ではなく、「後から入るほどデメリットが増える」というのが現実です。
▼それでも学資保険をおすすめしない理由
たとえ0歳から入ったとしても、学資保険には大きな弱点があります。
- 利回りが低く、インフレに勝てない
- 保険会社が倒産すれば元本保証はなし
- 長期間お金が拘束され、急な出費に対応できない
「早く入れば安心」という宣伝は魅力的に聞こえますが、インフレ時代にはリスクが大きすぎるのです。
▼私の結論
✅ 「入れる時期」は妊娠中〜小学校入学前まで
✅ でも「入れる時期が広い=安心」ではない
✅ どの時期でも、教育資金準備は 学資保険より「貯金+投資」 の方が合理的
少し目線を変えて、海外ではどのように【教育資金】を準備しているのでしょうか。
アメリカは物価も年収格差も日本と比べると大きい国。だいたいどんな制度があるのでしょうか。
▼アメリカの教育資金準備に学ぶ
日本は学資保険や貯金が中心ですが、アメリカではもっと多様な方法で準備をしています。
529プラン(学資積立制度) 日本の学資保険よりかなり柔軟な制度
- 州政府が運営する教育資金の積立制度
- 運用益が非課税、教育費に使うときに税制優遇あり
- 貯蓄型:ファンドを選んで運用
- 前払い型:将来の学費を固定価格で前払い
- 幼稚園〜大学まで利用可能、学生ローン返済にも使える
- 子ども(受益者)の変更も可能で柔軟性が高い←これ日本では考えられないですよね💦
助成金(スカラシップ)
- 返済不要の奨学金制度 が充実
- 国・州・大学・民間団体から成績や経済状況を基準に支給
- 多くの学生が複数の助成金を組み合わせて進学
学生ローン
- 授業料が高額なため、多くの学生が利用
- 卒業後に返済スタートするケースが多い
- 一方で「ローン残高の増大」が社会問題にも←日本でも卒業時500万程度の借金を背負っての社会人スタート。かなり厳しいですよね。
▼日本とアメリカの違い
- 日本:学資保険・銀行貯金中心
- アメリカ:投資型制度+給付型奨学金+学生ローン
- アメリカは「投資を活用した資金準備」「返済不要の助成金」が進んでいる
日本で取り入れられること
- 「529プラン」のような制度は日本にはないが、NISA制度を教育資金に活用できる
- 給付型奨学金は少しずつ拡充しているのでチェックが必要
- 子どもの誕生時から投資を含めて長期で積立をする発想は取り入れられる
▼貯金と投資を組み合わせるメリット
教育資金準備には 「確実性」と「インフレ対策」 の両立が大切。
シミュレーション例(年間25万円を教育資金として 貯金➕運用した場合)
- 貯金:13万円(利回り0%) → 18年後 234万円
- 投資:12万円(年利3%) → 18年後 285万円
- 合計: 519万円
インフレ後の必要額492万円をしっかり上回ります。
※ただし、全額投資はリスクが高いため「分散」が安心です。
教育資金に向く投資先
- オールカントリー(全世界株)
- S&P500(米国株)
過去データでは、20年以上保有すればほぼプラスの実績があります。
20年は待てないよー。
確かに・・・
ただ大学まで10年以上ある場合は、【投資】の方がいいと言われています。
わが家では、私はオールカントリー、夫はS&P500を選んでいます。夫婦で分けることでリスク分散にもなっています。ジュニアNISAに間に合わなかったとしても、銘柄を分けて投資しておくといいですよ。
<例>
オールカントリー(全世界株)・・・長女
S &P500・・・次女
というように、分けておくと、利確していざ使用したいときに、わかりやすいですね。
▼強制的に貯めたいなら「財形貯蓄」
- 元本割れなし、全額保護
- いつでも解約でき、流動性が高い
- 教育資金として転用しやすい
安心して貯めたい人にはおすすめです。
ただし、利回りが低い。
▼家計全体で資金を生み出す工夫
教育資金は「投資」だけでなく、家計改善でも加速できます。
- 固定費の見直し(通信費・保険・車関連費用など)
- 副業や在宅ワークで収入アップ
▼まとめ
- 学資保険は 低利回り+インフレに弱い
- 貯金+投資の組み合わせ でインフレに負けない教育資金づくりが可能
- 財形貯蓄や家計見直しも合わせれば、さらに準備がスムーズに
将来の教育費に不安を感じている方は、まず「貯金」と「投資」をバランスよく取り入れてみてくださいね。

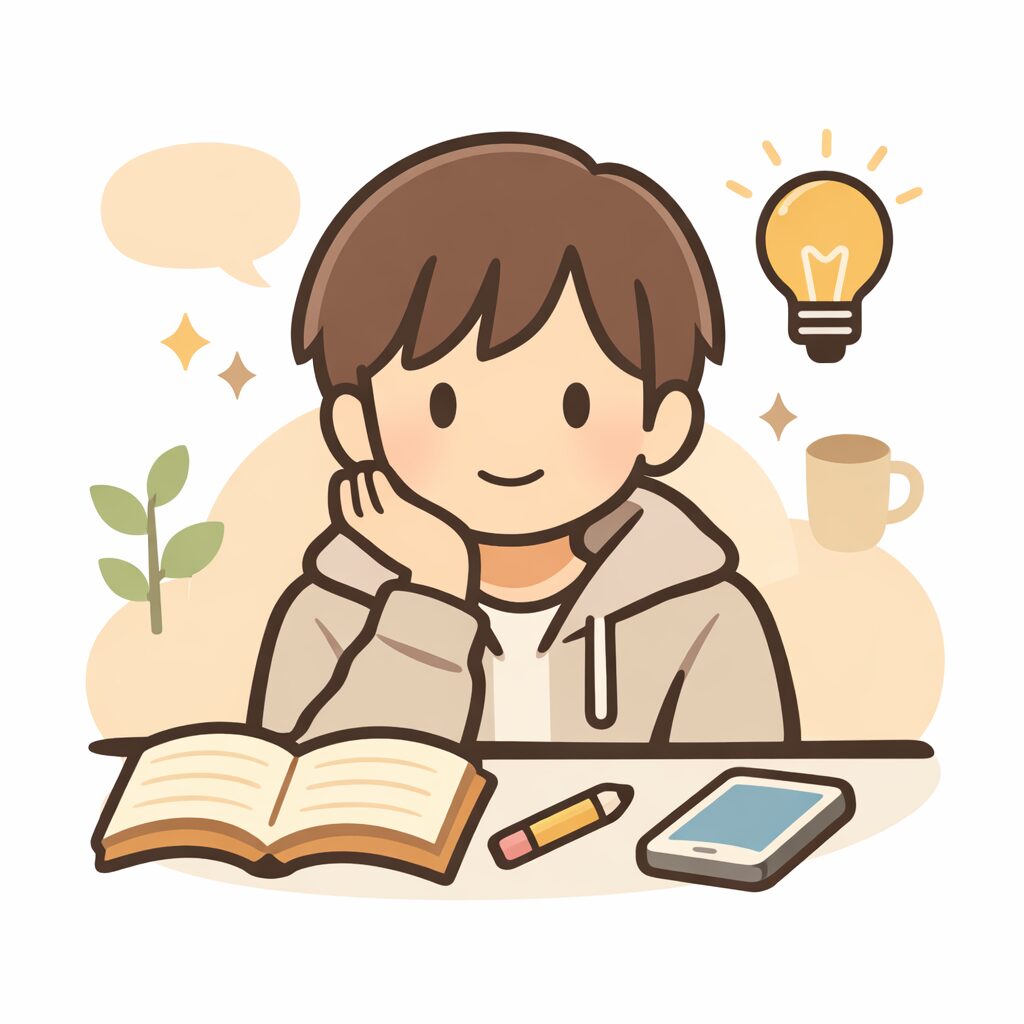
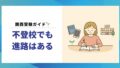

コメント